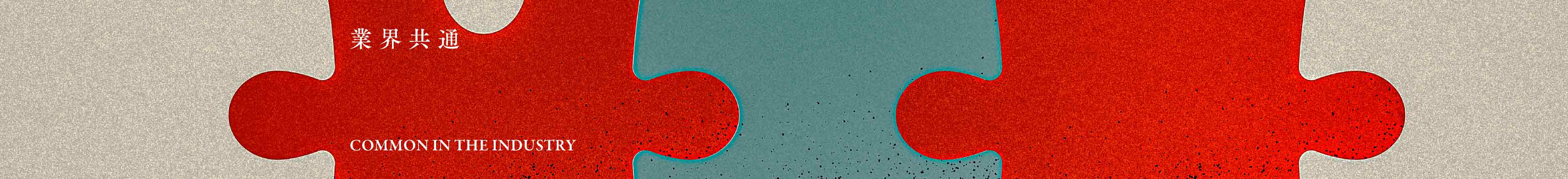(写真左)
(写真左)電通 第3統合ソリューション局 CXディレクション1部 部長 平嶋雅氏
(写真中央)
電通 第3統合ソリューション局 CXディレクション1部 シニア・ソリューション・ディレクター 天野徹氏
(写真右)
電通デジタル 執行役員 篭島俊亮氏
なぜ、DXはうまくいかないのか──。大きな要因の1つは「組織の壁」ではないだろうか。事業部門や部署の壁を乗り越え、データとデジタルを駆使して顧客に新たな価値を届けること。その結果として業績を向上させることがDXの成功であると考えれば、そのためには全社横断的な視点が重要だ。
例えばそれは「顧客起点」の視点である。いかにして顧客に最高の体験を届けるかということを起点にし、全部門・全社員の目線をそろえてこそはじめて組織の壁を乗り越え、さまざまな変革を成し遂げることができると考えられる。
ゆえに、DXの成功要件の1つとしてCX(顧客体験)は大きな意味を持つ。また、DXはCXを向上させるための手段の1つであると換言することもできる。
一方でCX向上の手段はDXに限らない。デジタルとアナログのさまざまな手段を組み合わせながら、顧客との接点(ブランド活動)を担う各部門・部署が連動して動くことで、シームレスな顧客体験をつくり出し、CX向上を実現することが可能になる。
今回のインタビューでは、DXを推進する上で欠かせない「CX」をテーマに、デジタルとアナログの両面で豊富な知見とケーパビリティーを持つ電通グループから、CX変革のエキスパート3名にご登場いただき、「DX課題から見えてきたCXの重要性とCX変革のヒント」について聞いた。
(聞き手:Japan Innovation Review編集長 瀬木友和)
「CX変革のためにDXを実行する」という視点の転換が必要
──平嶋さんは事業会社に出向し、DX推進チームに参画されたご経験もあるそうですが、DX推進やCX変革の現場では、企業の担当者からどのような悩み、不安の声が聞こえてきましたか。
 株式会社電通 第3統合ソリューション局 CXディレクション1部 部長 平嶋雅氏
株式会社電通 第3統合ソリューション局 CXディレクション1部 部長 平嶋雅氏
平嶋 私自身、全社最適と部門最適のバランスや一貫性を生み出すことに課題を感じていました。当時、DXの推進そのものは全社方針として決まっていたのですが、具体的にどのように進めていくかは現場に任されていました。本来DXには、全社の取り組みを有機的に統合するという目的があると思いますが、各部門の担当者は自部門のKPIを達成するために部門ごとに顧客にアプローチしていた状態で、DXが自部門の取り組みの高度化にとどまってしまうのではないかという懸念がありました。
また各部門の担当者には、「組織構造とKPIを変えない限り、全社最適の観点が各部のKPIを阻害するのではないか」という不安もあったように思います。
──DX推進の課題に対して、顧客起点の視点が解決のヒントになるとわれわれは考えていますが、CX変革を起こすには、どのような考え方や取り組みが有効ですか。
平嶋 前述の事例では、「どの部門が相手にしている顧客も同じ一人の人」であるという意識が浸透していったことで、DXの取り組みに一貫性が生まれました。
一人の人起点、顧客起点で考えると、企業内の部門・部署で分かれているあらゆるブランド活動はつながっていないといけません。つまり、DXを目的にするのではなく、顧客価値やCX変革のために必要なDXを実行するという視点の転換が必要だと私は思います。
そのためには、まず顧客を理解することが大切です。一言で顧客理解と言っても、お客さまについて知ることには、いろいろなレベル感があって、管掌している接点以外の顧客の生活全体が想像できていないこともあります。その結果、部門間で抜け落ちてしまう「ポテン課題」が生まれやすくなります。
例えば、金融デジタルサービスでは、顧客のサービス利用体験については把握できますが、その人のお金との付き合い方や、家族のお金の問題までは追いかけきれていないことがあります。そうした自分たちが見えていないところまで想像して顧客を理解することで、新たな価値を生み出すような課題が見つかってくるのではないでしょうか。
──部門間に隙間があってはならないわけですね。
平嶋 その隙間にこそ、イノベーションにつながりそうな課題が落ちていることが多いように思います。それを見つけたら、次に、どのような顧客価値を提供し、どう顧客体験をより良くするのかを考えます。このCXの変革方針があると、顧客視点で見たときに各部門のブランド活動は分断されていないか、1つのストーリーでつながっているかといったブランド活動の課題発見につながり、自ずと部署横断で取り組むべきサービス開発やDXが見えてきます。
その際、各部門の上位にNSM(ノース・スター・メトリック、北極星指標)を導入する考え方も有効です。各KPIをNSMに貢献する形で作り直すことで、各部門の取り組みが統合されていきます。
結果的に領域横断のCX変革を実現できた事業は、顧客視点での競争力を持ち、事業優位性の獲得にもつながると考えています。
意外に思われるかもしれませんが、大切なことは、CXの変革は各部門で行っている取り組みを起点に、全社に広げることができるという点です。
「組織の壁」を乗り越え、CX変革を起こす「4つのルート」とは
──CX変革を起こすために、電通グループではどのような支援を行っているのですか。
 株式会社電通 第3統合ソリューション局 シニア・ソリューション・ディレクター 天野徹氏
株式会社電通 第3統合ソリューション局 シニア・ソリューション・ディレクター 天野徹氏
天野 これまでさまざまな企業のCX変革を支援してきた中で、領域横断=組織横断の実現方法を、大きく4つのルートに体系化しています。
1つ目が「広告起点」。新規顧客獲得のための広告戦略のご相談から始まり、領域が広がっていくパターンです。新しいお客さまとの接点を生み出すだけでなく、その先にいかにファン化していくかを“地続き”で考えることで、広告だけでなく、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)など利用体験を含めたCX変革を行います。
2つ目が「データ起点」。顧客データの分析から始まり、領域が広がっていくパターンです。顧客理解を深めていく中で、インサイトをつかみ、それをサービス体験設計やコミュニケーション戦略など、領域を超えた顧客接点全体に反映させていくことでCX変革を行います。
3つ目が「パーパス起点」。ブランドの本質的な提供価値に立ち戻るプロセスから始まり、領域が広がっていくパターンです。ブランドのパーパスやビジョンなど言葉を作るだけでなく、その価値が伝わるように顧客接点全体に反映させていくことでCX変革を行います。
そして、4つ目が「CRM施策起点」です。SNS運用などのCRM施策から始まり、領域広がっていくパターンです。CRM施策を運用する中で、ファンのインサイトをつかみ、それを広告など新たなユーザー獲得施策にも反映させていくことでCX変革を行います。
これらに共通するポイントは、何もないところからCX変革を起こしていくのではなく、既存のマーケティング活動を起点にCX変革へと拡張していくアプローチであることです。いきなり「CXを変革する」といっても何から始めていいか分からないですし、非常にハードルが高くなります。そうではなく、既存の活動を起点とすることで、どんな企業でもCX変革を起こしていくことが可能になります。
「このルートから進めないとダメ」ということはなくて、むしろどのルートからでもCX変革を起こしていけるということも大きな特徴であり、われわれの支援の強みでもあると考えます。
 (図1)領域横断=組織横断の4つの起点
(図1)領域横断=組織横断の4つの起点拡大画像表示
──CX変革の具体的な事例について、いくつかご紹介ください。
天野 ルート③パーパス起点でCX変革を実現した飲食業界の事例があります。コロナ禍での行動制限により、生活者の意識や行動が一変したことをきっかけに、改めてブランドのコアバリューが何なのかを見直すところから始めました。
われわれは、コアバリューに合わせてCXの在り方も変えていくべきというご提案をさせていただき、各部門の方々と連携しながら、商品・サービスのラインアップを変えたり、広告のターゲットやクリエーティブの方向性を変えたり、さらには、これまでなかった購入後の新たな顧客接点をつくるといった形で、CX全体を変革していきました。
結果的には、ビジネスの成果にもつながり、競合他社が生活者の変化に対応できずに苦戦する中で、同社は一人勝ちと言われるような状況をつくることに成功しました。
平嶋 ルート②データ起点でCX変革を行った「生活基盤アプリ」の事例を紹介します。ある生活基盤アプリでは、1つのアプリサービスを複数の部署が担当し、基盤開発、UI開発、サービス運用、マーケティング、広告と、それぞれを別の部署が異なるKPIを持って運用していました。
そこで、われわれ電通グループは、最終的な事業KGIを共に担い、各部門を顧客視点でつなぐ“横串担当”となることをご提案し、関連する各部門と個別に向き合いながら、顧客視点で1つのストーリーを生み出す取り組みをしました。
具体的には利用データの分析を行い、顧客の生の声を聞いて顧客理解を深めていく中で、競合各社のキャンペーン集中に伴い、顧客が日々利用するサービス選択が難しくなってきているという課題に着目しました。そこでブランドポジションを見直し、顧客が選びやすく、継続する価値を向上する新たなサービス開発を軸に、マーケティング活動や広告活動を一気通貫で変革していきました。
 (図2)生活基盤アプリ事業のグロース支援
(図2)生活基盤アプリ事業のグロース支援拡大画像表示
篭島 同じくルート②データ起点によるCX変革を行った金融業の事例があります。コロナ禍によって非対面サービスのニーズが高まるなど、お客さまが求めるサービス体験が変化していく中で、同社ではアプリやウェブサイトなどデジタル接点の強化が進行していました。その中で得られる行動データを統合・分析し、お客さま理解の高度化や迅速なマーケティング施策への反映といったアクションにつなげるために、われわれはマーケティングプラットフォームの構築をご支援しました。
さらに、構築して終わりではなく、お客さまのニーズ・関心に合わせて最適なご提案をしていくためにどうデータを使っていくか、CRMから広告の配信まで、継続的にPDCAを回しながら幅広い支援を行っています。
 (図3)マーケティングプラットフォーム構築の支援
(図3)マーケティングプラットフォーム構築の支援拡大画像表示
データの時代に改めて見直される「顧客を想像する仮説力」
──CX変革やCX向上支援における電通グループの強み、特長はどこにあるとお考えですか。
平嶋 前提として、環境変化に対応するためだけではなく、新たな価値を生み出していくのがわれわれの考えるCX変革であるということです。課題を見つけ、それを解決し、新たな価値を提供する。そこに向けた全社の取り組みを統一感あるものにしていくのがわれわれのCX変革支援の特長です。そのベースとなる強みはプランニング上、3つあると思っています。
1つ目は「顧客を想像する仮説力」です。顧客を想像する仮説力については近年、再び重要性が増していると考えています。背景には、あらゆるビジネス接点がデジタル化されたことで、お客さまの様子が分かるリアルチャネルと異なり、企業から見えにくい顧客の課題が増えてきたことがあります。その動きがコロナ禍で加速したのが現在です。
今はデータ活用を高度化させることに加えて、可視化できるデータを基に、顧客を想像する力が重視されるようになりました。「こうすれば人が動いてくれるのではないか」という仮説力こそ、CX変革を実現する大きなファクターとなります。
2つ目は「夢やビジョンを描く力」で、電通グループが元々自信のある領域です。デジタル上では企業と顧客が一対一でつながることができますが、課題が細分化されていく世界です。一方で、顧客に新たな価値を提供する際は、夢を描く力が必要で、それはマスマーケティングで培ってきた力だと思います。
3つ目が「部署や領域を横断する統合的なプロデュース力」で、電通グループの社内文化に起因するものです。私が事業会社に出向した際に外から電通を見て強く感じたことですが、電通グループは部署の壁が低く、全員が全領域を考え、同じ方向を向いて動く文化があります。外部の立場からこの統合的なプロデュースを行うことで、社内の統合がうまくいくケースが多くあります。
 電通デジタル 執行役員 篭島俊亮氏
電通デジタル 執行役員 篭島俊亮氏
篭島 まさにその3つの力が重要ですが、それを支えるエグゼキューション力(実行力)も、もう1つの強みです。われわれはクライアントと一緒に描いたビジョンや設計を、しっかり形にしていく、そのエグゼキューションまでワンストップで対応することが可能です。電通デジタルを含め、高度な専門性を有したグループ企業が柔軟にチームを組むことで、“絵に描いた餅”に終わらない支援ができると考えています。
──最後にDX推進担当者、企業変革のリーダーに向けてメッセージをお願いします。
平嶋 DX推進や企業変革の鍵を握るCXの変革は、どの領域からでも始められます。皆さんも顧客起点で領域横断=組織横断をドライブし、ぜひCX変革にチャレンジしてほしいと思います。

インタビューを終えて
Japan Innovation Review 編集長 瀬木 友和
「CX(カスタマーエクスペリエンス)」という言葉は難しい。日本語にすると「顧客体験」である。なんだか、分かるようで分からない。それゆえ、人や企業によって受け止め方がばらばらになりがちなのだ。取材活動を行う中で、取材先から「CX」という話が出てくると、私は一瞬身構える。「この人のCXは何の話だろう」と。ある人はパーソナライゼーションの話をしているのかもしれないし、ある人はスマートフォンのアプリの話をしているのもしれない。はたまたビジネスモデルの変革やDX(デジタルトランスフォーション)そのものの話をしている場合だってある。
もちろん、教科書的な定義は存在する。マーケティング論の権威、フィリップ・コトラー氏は著書『コトラーのマーケティング5.0』の中で以下のように述べている。
「CXは購入体験や顧客サービスだけを意味するものではない。それどころか、顧客が製品を購入するずっと前から始まり、購入後もずっと続くのだ。CXは顧客が製品に触れる可能性のあるすべてのタッチポイント――ブランド・コミュニケーション、小売体験、販売員とのインタラクション、製品の使用、顧客サービス、他の顧客との会話――を包含している。顧客にとって意味があり、しかも忘れがたいシームレスなCXを提供するためには、企業はこれらすべてのタッチポイントを統合しなければならない」
※引用:『コトラーのマーケティング5.0 デジタル・テクノロジー時代の革新戦略』(朝日新聞出版、著・フィリップ・コトラー、ヘルマワン・カルタジャヤ、イワン・セティアワン、監訳・恩藏直人、訳・藤井清美)
つまり、CXの要(かなめ)は「シームレスに顧客のあらゆる接点を“統合”すること」にある。だが、多くの企業ではそれこそが難しい。どうしても、部署・部門間の壁が立ちはだかるからだ。それゆえに、CXという言葉の受け止め方が人や企業によってばらついているのだと思う。一般的に部署・部門の壁を超えるためには全体を統べる強力なリーダーシップが必要だが、CXという文脈においてその役割や権限を有するポジションを設置している企業は少ない。このために、日本企業ではCX変革がなかなかうまくいかないのだ、と私は考えていた。
しかし、である。電通グループのエキスパートたちは「それでいい」と言う。インタビューの中で天野氏が説明してくれたとおり、すでに各部署・部門が担っている「広告」「データ」「パーパス」「CRM施策」という4つの施策を起点とし、徐々に領域を拡大・結合させ、最終的に全体をシームレスに統合させるというアプローチが有効だと言うのだ。
まさに、目から鱗である。何もないところからいきなり全体を統合したCX変革を起こすというアプローチよりはるかに現実的であり、「それなら自分でもできそうだ」と考える人も多いのではないだろうか。そう、大事なのは、全社的なCX変革の起点に一人ひとりがなれるという可能性だ。それは「志」とも言い換えられるだろう。CX変革を「自分起点」で起こしたいという志を抱く方がいたら、まずは電通グループのエキスパートたちに壁打ち相手になってもらってはいかがだろうか。
<PR>
dentsu Japanのコーポレートサイトはこちら
dentsu Japanへのお問い合わせ:japan-cc@dentsu-group.com