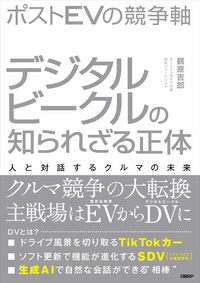技術ジャーナリスト・編集者の鶴原 吉郎氏(撮影:榊水麗)
技術ジャーナリスト・編集者の鶴原 吉郎氏(撮影:榊水麗)
自動車産業が大きな転換期を迎え、電気自動車(EV)へのシフトが進む中、その先にあるクルマ像についての新たな視点も現れ始めている。技術ジャーナリストの鶴原吉郎氏は、著書『ポストEVの競争軸 デジタルビークルの知られざる正体 人と対話するクルマの未来』(日経BP)で次世代自動車を「デジタルビークル(DV)」と呼び、これからのクルマの在り方を考える上で重要な視点を提供している。
DVの概念と可能性について聞いた前編に続き、後編では、中国が主導するDVを巡るグローバル競争の現状、DVの時代において日本の自動車産業が直面する課題や展望などについて同氏に尋ねた。(後編/全2回)
■【前編】中国の急速な台頭で見落としてはいけない、自動車の「デジタルビークル」化が生み出す新たな競争軸
■【後編】先頭を走るのはやはりトヨタか? 「デジタルビークル」視点で占う自動車産業のこれからの勢力図(今回)
中国の強さはどこから来るのか?
──著書『ポストEVの競争軸 デジタルビークルの知られざる正体』の中で、自動車強国を目指す中国がEVに続いて主導しているのがDVだとしていますが、中国の自動車産業は具体的にはどのような状況にあるのでしょうか?
鶴原吉郎氏(以下敬称略) 中国がDVのような次世代のクルマにおいて競争力を持つ背景には、自動車産業に携わる人の年齢層が圧倒的に若いことがあります。
例えば欧米や日本の自動車メーカーで開発の中枢にいる人たちは40~50代が中心です。彼らはクルマといえばエンジンやサスペンション、ボディーといった機械的な要素に心を奪われてきた世代で、クルマそのものの価値も、価値のつくり方も大きく変化しているDVのような存在は、頭では理解できてもエモーションの部分がついていっていないように見受けられます。
一方、中国の自動車メーカーはBYDにしてもジーリーにしても、20〜30代のエンジニアが、若いエネルギーと自由な感性で従来の価値観にとらわれることなくクルマを開発しています。
鶴原 彼らの作るクルマは、例えば軽自動車のようなコンパクトカーでも、シンプルで洗練されたデザインのインパネに大きな液晶ディスプレイだけが装着されていて、車両の周囲を映し出すスタイリッシュな3D映像をタッチパネルで動かしながら安全を確認したりすることが可能です。
 ジーリー傘下のボルボのコンパクトEV「EX30」のインテリア。車内に物理スイッチはほぼ存在しないが、ステアリングコラムのレバーを下げるだけで運転支援機能が作動するなどストレスのない操作を実現している(出所:ボルボ)
ジーリー傘下のボルボのコンパクトEV「EX30」のインテリア。車内に物理スイッチはほぼ存在しないが、ステアリングコラムのレバーを下げるだけで運転支援機能が作動するなどストレスのない操作を実現している(出所:ボルボ)
クルマの本質とは関係ないギミックといえばその通りですが、UI(ユーザーインターフェース)の斬新さだとか、それらがもたらす体験価値といった点で、日欧米のクルマとは別次元にあると感じています。タイのモーターショーで中国車、日本車、ヨーロッパ車、そしてアメリカ車が展示されているのを見た時のことですが、中国車の新しさは歴然としていました。これは技術力ではなく感覚の問題なのですが、こうした部分も中国が次世代のクルマをけん引していると思わせる要素です。
 2024年北京モーターショーにおけるジーリーの出展ブース(出所:ジーリー)
2024年北京モーターショーにおけるジーリーの出展ブース(出所:ジーリー)
──自動車産業の従事者が若いことの他に、中国がDVを主導している要因はありますか?
鶴原 他業種から新しい発想を持って自動車業界に参入する動きが活発なのも一因です。
例えば、今ファーウェイが中国の自動車産業において勢力を伸ばしています。もちろん彼らにはクルマ開発の経験はありませんが、AI(人工知能)、センサー、カメラ、そして通信システムといった、通信機器メーカーとして培ってきた豊富な技術があります。彼らはそうしたテクノロジーを、例えば自動運転のソフトウエアやセンサー、あるいは頭脳となる半導体などに応用しているわけです。
スマートフォンや家電を手掛けるシャオミのような企業も、中国におけるクルマのDV化において重要な役割を果たしています。今や家や家電など全てがネットワークでつながり、スマホのアプリでエアコンをコントロールしたり、冷蔵庫の中を確認したりすることが一般的ですが、そうしたシャオミの生態系にクルマを組み込むことで、前編でお話ししたようにクルマが新たな価値を生み出すことが可能になるのです。
また、彼らのようなテクノロジー企業は、例えばUI設計などにおいても欧米や日本の自動車メーカーにはないノウハウや独創的なアイデアがあります。中国車のUIに新しさがあるのは、そうした異業種のノウハウが生かされているからでもあります。
アメリカ、日本、欧州の動向は?
──DV競争を主導する中国に対して、欧米や日本はどのような状況にあるのでしょうか?
鶴原 アメリカについては、例えばグーグルのグループ会社であるウェイモが自動運転システムの開発に取り組むなど、中国と同様にテック企業をはじめとする他業種からの参入に期待が持てます。クルマに求められる価値が変化する中で、彼らは自動車メーカーにないアイデアやノウハウを次世代のクルマ作りに生かしていこうというわけです。
その点で、私はアマゾンに可能性があると感じています。彼らはすでに巨大な倉庫内の物流を自動化していますが、将来的には一般道でも自動運転によるトラックやバンが配送を担うことになるでしょう。さらに、そうした配送インフラが整えば、一部を一般に開放して物流や人流のサービスを提供することも考えられます。安全性の面などでハードルは存在しますが、社内用のインフラを一般向けサービスとして展開するというビジネスモデルはAWS(アマゾン・ウェブ・サービス)に見られるようにアマゾンの得意とするところですし、DV時代のモビリティ社会に貢献してくれる可能性が高いのではと考えています。
 アマゾンが物流拠点「フルフィルメントセンター(FC)」で導入している自走式ロボット。この小さなロボットが商品棚を自動でスタッフのいる場所に運ぶ(出所:アマゾン)
アマゾンが物流拠点「フルフィルメントセンター(FC)」で導入している自走式ロボット。この小さなロボットが商品棚を自動でスタッフのいる場所に運ぶ(出所:アマゾン)
──日本には大きな自動車メーカーが多数存在し、ハイブリッドをはじめとする高い技術力を誇る自動車大国ですが、DV時代への変革に対応ができているのでしょうか?
鶴原 各メーカーは変革への取り組みを始めています。その点で先頭を走っているのはトヨタでしょう。豊田章男会長はエンジンサウンドやガソリンの香りが好きだと公言するカーガイですが、2018年のCES(Consumer Electronic Show)では、トヨタがクルマ会社であることを超え、人々のさまざまな移動を支えるモビリティ・カンパニーへと変革することを宣言しています。
実際、グループ会社のウーヴン・バイ・トヨタでは、「アリーンOS」などソフトウエアを基盤としたモビリティの技術開発を進めています。まさにDV時代に向けた取り組みといえるでしょう。
日産はといえば、例えば「もっと自由な移動を」をコンセプトに、自動運転車を用いた新しい移動サービス「イージーライド」をDeNAと共同開発し、2017年より継続的に実証実験に取り組んでいます。
このサービスが興味深いのは、例えばあるカフェに近づくと、利用者のスマホを通してカフェで利用できるクーポンを提供するなど、単なる移動サービスにとどまらない体験や、街の活性化といった、新たな価値を生み出そうとしている点です。
スバル、スズキ、ダイハツといった比較的企業規模がコンパクトな会社は独自に取り組むというよりは、大手企業が開発するOS、プラットフォーム、ネットワークに相乗りさせてもらう、といったスタンスなのかなと感じます。

──欧州メーカーについてはどうでしょうか?
鶴原 欧米メーカーは概して従来のクルマ作りの価値観にとらわれがちで、新しい価値の創造に苦戦しているように感じます。
前編でお話しした通り、欧州メーカーは経営資源をEV開発に集中させてきたのですが、ここにきて各国の市場でEVが失速したこともあり、次世代への投資という点でも難しい状況に置かれています。
今、中国のメーカーがDVのキラーコンテンツとして位置付けているものの一つは自動運転です。自動運転に限らず、DV向けのキラーコンテンツが中国から生まれた後に彼らを追いかけるのでは決して間に合いません。その意味で、日本や欧米の自動車産業は、今こそ全身全霊を懸けて、自動車を再発明するくらいの意気込みでDVの開発に取り組む必要があるのではないでしょうか。
■【前編】中国の急速な台頭で見落としてはいけない、自動車の「デジタルビークル」化が生み出す新たな競争軸
■【後編】先頭を走るのはやはりトヨタか? 「デジタルビークル」視点で占う自動車産業のこれからの勢力図(今回)