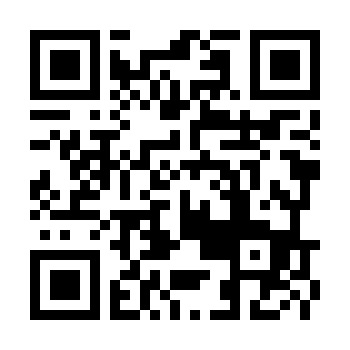化学業界を代表する企業の一つ、旭化成。マテリアル・住宅・ヘルスケア各事業のデジタル変革と、それらに共通する全社的デジタル基盤の強化を図るデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めている。経済産業省「DX銘柄」には2021年から3年連続で選定された。だが、「デジタル化は遅い」と評される日本の化学業界において、同社もその例外ではなかった。デジタル技術の導入から展開、さらに創造へと急速な歩みを遂げる裏には、「指揮者」の着任と様々な試行錯誤があった。
「日本は全然だめだ」遅々としていた化学業界のデジタル化
「デジタルを活用する組織風土が一気に事業活動に染み込み、血肉となっていると感じています。強化されたグループ共通のデジタル基盤をベースに、経営の高度化、そしてビジネス変革を進め、成果発現のフェーズへ進みます」
2023年4月11日。旭化成の2024年度までの中期経営計画の進捗状況説明会で、代表取締役社長の工藤幸四郎氏はこう述べた。同社は言わずと知れた大手総合化学メーカー。従業員は連結でグローバル4万8,897人(2023年3月時点) にのぼる。巨大メーカーがデジタル活用をいかに進めているかは、多くの人びとが注目するところだ。
化学分野のDXとして「マテリアルズ・インフォマティクス」(MI)を思い浮かべる人は多いだろう。人工知能技術を応用して、材料開発の効率を高める取り組みだ。実際、同社は2017年からMIを推進している(これについては次回の第2回で取り上げる)。
しかしながら、日本の化学企業は、専門家たちから「総じて欧米の先行企業よりデジタル化が遅い」と指摘されてきた。背景として、特化した隙間領域を強みとする企業が多く、投資が割に合わないといったことや、デジタル技術なしでも良質な材料・製品を生み出すことができ、デジタル化の必要性が高まらなかったことなどがいわれる。
2010年代後半、旭化成の社内にも、特に国内事業におけるデジタル技術導入の遅れに対する危惧はあったようだ。事業拡大のため米国企業を買収したところ、その企業の従業員たちのデジタルリテラシーの高さや、モノのインターネット(IoT)技術を駆使したビジネスの進み具合に、「日本は全然だめだ」と感じた人物もいた。
そうした中、同社DX推進の「指揮者」に就いた人物がいる。久世和資氏だ。
100年歩んできた企業が、2年で段階を上げる
久世氏は1987年、日本IBMに入社し、研究や開発といった技術畑を歩み、同社事業を牽引してきた。2017年に日本IBMとしては初となる最高技術責任者(CTO)となった。
「2020年が日本IBMでの役員任期満了期でした。その年の1月、日本CTOフォーラムで知り合い、10年以上交流があった旭化成の役員から、旭化成のDXに対する取組みについてお話を伺う機会がありました。」
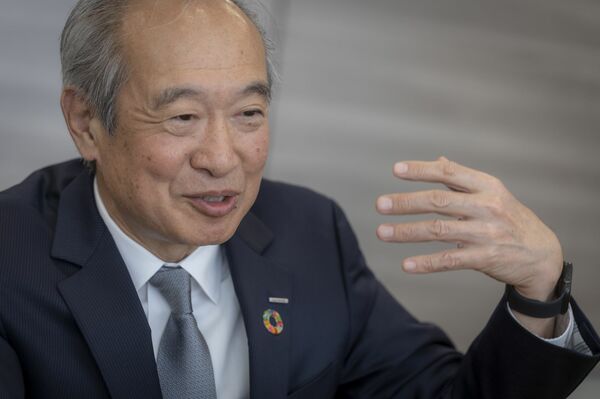 旭化成 取締役 兼 専務執行役員 デジタル共創本部長 久世和資氏(撮影:酒井俊春)
旭化成 取締役 兼 専務執行役員 デジタル共創本部長 久世和資氏(撮影:酒井俊春)
その際、研究・開発と生産・製造を中心にDXを推進していること、全社展開が次の課題であること、さらには、グローバルレベルのデジタルによる事業変革が課題であることが伝えられた。
端的にいえば、久世氏に期待がかけられたのだ。
「お話を聞くと、マテリアルズ・インフォマティクスによる圧倒的なスピードでの素材開発や革新素材の開発に積極的に取り組んでいることがよく理解できました。また、製造生産現場での高度なデータ分析によるテストの自動化、品質の改善、生産性の抜本的な向上など多くの先進的な取り組みを知ることもできました。私が日本の化学業界に抱いていた印象、つまり、世界でも強力な技術力と事業力を持ちながら、デジタル技術はあまり活用できていないという印象と違い、かなり先進的に取り組んでいると感じました。IBM時代から現場には頻繁に足を運んでいたので、宮崎県の延岡地区の工場や岡山県の水島製造所などの現場に訪問したかったのですが、コロナ禍で実現できませんでした。それでも、研究・開発と生産・製造で、それぞれ、DXを立ち上げてリードしてきた河野氏(現・インフォマティクス推進センター長)と原田氏(現・DX 経営推進センター長)の話を聞き、彼らの現場密着でDXを推進する姿勢と変革達成に向けた熱意に感銘を受け、入社を決めました。デジタル技術を使えば日本が強みとしている化学産業に対して、もっといろいろなことができる。日本の化学産業の中で進んでいるのはここ旭化成だと」
こうして2020年7月、久世氏は旭化成の執行役員・エグゼクティブフェローに就任した。
旭化成にきて早々、久世氏がDXを推進するリーダーたちと策定したのが「デジタル変革のロードマップ」だ。「デジタル導入期」を経て、「展開期」「創造期」「ノーマル期」へと2年ごとに進んでいく。
「2年間で節目を迎えて次に進むのは、約100年の歴史がある企業からすると早すぎると、他のメンバーから思われました。けれどもスピードが必要と考え、短く区切っていきました。当時の展開期の課題は、研究・開発、生産・製造など部門によりデジタル化の進み具合が異なる中、いかに全社的にDXを広げるかでした」
2023年のいまは「創造期」にあたる。デジタル技術をきっかけに、新しい価値を創造していくという意味を込めている。さらに2024年からは、「ノーマル期」へと進んでいく。全従業員がデジタル技術を特別視しないで仕事や業務に使えている状況をめざすという。
また、全従業員向けのDX教育の仕組みとして、習得したデジタル技術のレベル別に「オープンバッジ」とよばれるデジタル認証を発行するなどの仕組みを整えた。これら人材育成については第7回で取り上げる。
「人、データ、組織風土」に込めた「DXは技術にあらず」の意味
旭化成に着任してから9カ月後の2021年4月、久世氏は旭化成に発足したデジタル共創本部の本部長となる。この本部は、デジタルと共創による旭化成の変革をグループ横断的に推進するためのものだ。
いわば全社的なDXを推進する部隊ができ、久世氏という指揮者が就いたことになる。体制は固まっていったように見える。一方、デジタル共創本部のメンバーらと課題を話し合う中で、よりソフト的な点にDXの成功要因が見えてきたと久世氏は言う。
一つ目は「人」だ。「人は大事です。しかし、営業・マーケティング、研究・開発、生産・製造などの現場で、まだまだDX人材が足りていません。外から優秀な人材をキャリア採用することも大切ですが、できるだけ、いま現場で活躍している従業員一人一人が、デジタルをきっかけに、仕事や業務の変革を推進できる人材となることを目指しています。スピードアップするには、情報技術やデジタル技術の最低限のリテラシーをもち、何が難しいか、どこが課題かを理解できる能力とスキルを持つことが必要です」
二つ目は「データ」である。「旭化成にきたとき、自由闊達な組織風土や上司部下の風通しのよさを感じた一方、マテリアル・住宅・ヘルスケアの事業領域間でも、また、各事業部間でも、データが十分に共有できていませんでした。 組織の壁を超えて、質の高いデータを共有することで新しい価値は創れるものです。さらに、企業の壁さえも超えてデータがつながると、創れる価値はより大きくなる。これを実現できるかどうかは日本の重要な課題でもあります」
三つ目が「組織風土」だ。「みんなで変革を遂げていこうという考え方です。DXを個人や個々の組織だけでなく、一丸となって進める風土がないとスピードが出ません。異なる組織どうし、壁を超えて共創していく考え方も大切です」
人、データ、組織風土。これらがDXの成功要因だという久世氏の話は、とかくDXにおいて技術面に関心が向けられがちなことに対するアンチテーゼと捉えられる。つまり、旭化成従業員たちへの「単なる技術導入とは違うものだという心をもってもらいたい」(久世氏)というメッセージでもある。

推進に呼応する従業員たち
「正直にいえば、2年ごとに次の段階に進める自信があったわけではありません。しかし、研究・開発などでデジタル技術を駆使できる人が育ってきています。やればできると考えてやってきました。KPI(重要業績評価指標)を見るかぎり、DXの進捗は順調に行っていると思います」
こう話す久世氏が、旭化成のDX推進のリーダーの一人であることは間違いない。一方で、代表取締役社長である工藤氏が直接管轄する「CEOマイルストーン」とよぶDXテーマがあることも久世氏は強調する。「たとえば、経営ダッシュボード。これは、経営の見える化を加速するテーマです。より一層データを活用し、世界の動きや経営環境の変化に対し、重要となるデータを迅速に捉え、データドリブン経営を目指すものです」(久世氏)。他にカーボンフットプリントの見える化など、500超の取り組みのうち全社共通の重要テーマなど8件が、CEOマイルストーンとなっている。
ここまでの旭化成のDXを俯瞰してみるとどうなるか。「デジタル導入期」は2016年ごろからだ。日本の化学業界全体にいえる「遅い」デジタル化の出だしと一致する。だがその後、特に久世氏が同社に着任して以降、急速にDXの歩みを進めている。非デジタル企業からDX企業へ。ここ数年で変貌を遂げたと見ることができる。
「DXのネタを提供したり、共創を加速させるのは私たちデジタル共創本部の役割です。一方で、現場の人たちが自分たちでデータを分析する動きが始まっています」と久世氏は言う。DXの推進に呼応する従業員たちがいる。
次回以降、事業やプロジェクトごとに旭化成におけるDXを追っていくことにする。