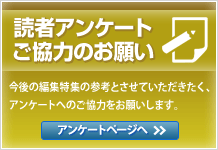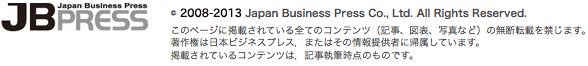上の説明で、サーバが老朽化しても使い続けることのリスクは十分に理解していただけたことと思う。まずは、こうした目下のリスクを解消していくこと、いわば「守りのIT投資」が、経営を変えるITの出発点となる。
もし、あなたの企業が典型的な「何もしない、何も変えない」体質の組織だったとしても、新規の業務システムが必要になったタイミングで、最新のPCサーバを1台導入し、その効果を体感していただきたい。もちろん、予算の問題はあるだろうが、PCサーバ製品はここ数年で、コストパフォーマンスが大幅に増しており、老朽化したサーバをそのまま使い続けることで生じる種々のリスクを、経営陣や事業部門リーダーにきちんと説明すれば、たいては重い腰を上げるはずだ。
最新のCPUを導入すれば、やはり従来機種からの性能アップと消費電力の軽減などを実現できる。これらの点を、富士通のPCサーバ「PRIMERGY(プライマジー)」を例に説明していきたい。エントリー向けとして低価格レンジながらも、処理性能や信頼性の高さ、導入・運用・メンテナンス時の使い勝手の良さ、低消費電力・省スペースボディなど数々の特長を備えたPRIMERGYは、中堅・中小企業の部門サーバや基幹業務サーバの用途においても豊富な導入実績を持っている。
前段で挙げたリスクへの直接的な解を含む、PRIMERGYの主な特長・機能をピックアップしてみる。
①高信頼と品質
導入から運用までの全てのフェーズにおいて、厳密な品質管理が行われることで実現される高い信頼性は、「価格が安いだけのPCサーバ」とは一線を画す魅力である。PRIMERGYの場合、開発プロセスで、日本ならではの地震を想定した振動試験を実施し、耐久性を高め、信頼性を担保している。加えて、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースにPRIMERGY本体の製造(部品受入検査・CPU組み込み・装置組込・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを国内で実施し、Made in Japanとしての高品質をユーザーに届けている。
②省エネ・節電の追求
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)への対処として、2011年度までに達成が義務づけられた目標基準値をクリアしているかどうかもポイントだ。その点、PRIMERGYはCPUの周波数制御、消費電力履歴のグラフ表示など、省エネ・節電に寄与するさまざまな機能が備わっており、サーバルームの電力・空調コストも大幅に抑えることが可能になる。実際に、とあるモデル(*)では、消費電力を約49%も削減するなど、実際に数値化された効果を確認することもできる。
*PRIMERGY TX200 S5と当社従来モデルとの比較
③使い勝手と静音性の追求
ちょっとした使い勝手の良さへのこだわりも見逃せない。PRIMERGYには、ハードディスクからのデータ盗難やサーバの盗難を防止する機構が備わっているので、タワー型サーバではハードディスクや電源スイッチをロックできるフロント保護機構を装備しており、サーバのカバーもロックすることが可能になっている。加えて、PCサーバを設置するオフィス環境ならではの音響上の制限(オフィス環境での稼働音など)を意識しているかどうかも大切となる。この点については、製品自体に備わった静音性への配慮が鍵となる。PRIMERGYの場合、「ささやき声」レベルの静音化(稼働時32dB)を実現したモデルもラインアップしており、ユーザーに快適な作業環境をもたらすことを追求している。また、標準のサーバ運用管理ソフトウェア(※)に備わる多彩な通知機能(ポップアップメッセージ、PCやモバイルデバイスへのメール通知、SNMPトラップ転送、警告灯通知など)の活用により、サーバ管理者は、いつ、どのコンポーネントに異常が発生したのかをリアルタイムで把握できるようになる。リモート操作用のプロセッサ「リモートマネジメントコントローラ」も搭載しており、遠隔地にあるサーバ操作も可能になる。柔軟に操作環境を実現することで、サーバの設置場所に移動する時間やコストを削減し、サーバ管理者の負荷は、ずいぶんと軽減されることになろう。
また、ゼロ情シスや孤独な1人情シスの社員にとっては、製品の性能・機能だけでなく、保守運用支援サービスも押さえておくべきポイントの一つである。
富士通では、サポートセンターと全国のサービス拠点が緊密に連携し、サポート/サービスを提供できる体制を整えている。加えて、万が一のシステム障害発生時に、24時間・365日対応でお客様の下へ担当エンジニアを派遣し、迅速に対処できるようになっている。
* * *
以上、本稿では、中堅・中小企業における典型的な課題をあげながら、「経営を変えるIT」が浸透していかない理由について考察した。まずは「守り=リスクの解消」から始め、最新のITがもたらす効果を実感したうえで、「攻め=経営効率改善に直接貢献するIT活用」に転じていく。これによって、経営陣や事業部門リーダー、そして現場の社員の間で、ビジネスでのIT活用に対する考え方が一転し、「経営を変えるIT」に向かってなすべきことが見えてくるはずだ。