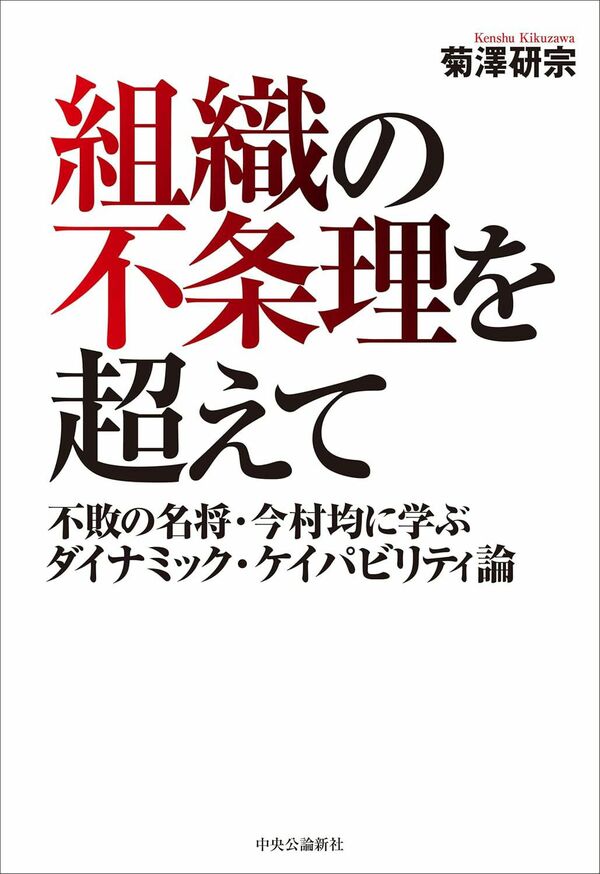出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
「戦場で一度も負けなかった」とされる帝国陸軍大将・今村均。そのマネジメント手法について「現代の日本企業が直面する危機を乗り越えるための示唆が隠されている」と語るのは、2025年8月に著書『組織の不条理を超えて 不敗の名将・今村均に学ぶダイナミック・ケイパビリティ論』を出版した慶應義塾大学名誉教授の菊澤研宗氏だ。時代を超えて今村均から学ぶべき観点、組織が変革力を発揮するための原理について同氏に聞いた。
成功した日本企業が直面する「不条理の罠」
――著書『組織の不条理を超えて』では、帝国陸軍大将・今村均のマネジメント手法、そこで発揮された組織能力「ダイナミック・ケイパビリティ」を題材としています。どのような理由から今回のテーマを選んだのでしょうか。
菊澤研宗氏(以下敬称略) 私が課題視しているのは、多くの日本企業がかつて成功した時代のビジネスモデルに固執し続けている点です。
時代の分岐点は、Windows95が登場した1995年でした。その前後で企業の事業環境は大きく変わったのです。インターネットの時代が到来する以前の日本企業は、少しでも成功するとそのビジネスモデルを徹底的に洗練させることで成功を収めてきました。
しかし、その後は急速なITの進化とグローバル化によって環境が激変したにもかかわらず、依然として過去の成功モデルの洗練化を続け、5カ年計画や中期経営計画という名のもとに同じことを二度、三度と繰り返してきたのです。
それはすなわち、日本企業の硬直化を意味します。個別企業としては合理的に行動しているはずが、外部環境との乖離(かいり)が広がり、結果的に淘汰されてしまうことを、私は「不条理の罠(わな)」と表現しています。
実は組織のリーダーたちは、不条理に陥っていることに気付き、既存のビジネスモデルの変革の必要性を認識しています。しかし変革を進めるには、必ず抵抗勢力と戦わなくてはいけません。
ここでリーダーは粘り強く抵抗勢力を抑えなければいけないのですが、賢い人ほどその説得コストの大きさを目の当たりにすると「何もしない方が合理的」という判断に陥り、変革に消極的になりがちです。
これこそが今、日本企業が抱える根本的な問題だと考えています。そして、この問題を打開するためのアプローチが「ダイナミック・ケイパビリティ」なのです。
組織の変革に有効な「ダイナミック・ケイパビリティ」とは何か?
――ダイナミック・ケイパビリティとは、どのような組織能力を指すのでしょうか。
菊澤 ダイナミック・ケイパビリティの概念を提唱した米カリフォルニア大学バークレー校のデビッド・ティース教授によると、企業能力は大きく2つに分かれます。
1つは、既存のビジネスモデルのもとで効率性を追求する「オーディナリー・ケイパビリティ」。これは、オペレーション(業務遂行)能力と言い換えることもできます。もう1つが、環境変化に応じてビジネスモデルそのものを変革する能力で、これをダイナミック・ケイパビリティと呼びます。
ダイナミック・ケイパビリティは、オーディナリー・ケイパビリティより上位にあるメタレベルの能力で、①環境の変化をいち早く感知し、②その中に新しいビジネスの機会を見いだし、③既存資産を再構成して自己変革する、という3つの要素から成り立ちます。
この能力は企業のトップを務める個人の能力であると同時に、現場の感知力も含む組織全体の能力でもあります。
――著書では、旧日本陸軍の指揮官、今村均がダイナミック・ケイパビリティを発揮した事例の一つとして、インドネシア・ジャワ軍政を挙げています。ここではどのようなマネジメントを行ったのでしょうか。
菊澤 軍隊が海外で戦いに勝利して占領統治する際には、暴力をもって捕虜や住民を奴隷のように扱い、急進的に変革を進める軍事独裁に陥るケースが多くみられます。
ところが、今村均はその逆を行い、これまでの伝統や歴史を継承しつつ、住民にさまざまな権利を与え、軍事システム・農業技術・水害対策などの知識を惜しみなく提供し、漸次的に改革を進めました。強制労働ではなく「働いた分は正当に給料を払う」「ある程度の自由時間や休暇日を認める」ことで、彼らのモチベーションを高め、現地住民による自律的な統治を促したのです。
これは「所有権理論の原理」に基づいています。自らの労働の所有権を住民に与えることで、自分が働いた分はリターンとして戻ってくるという関係を明確にしたことで、やればやるだけ得をするし、さぼればさぼっただけ何も入ってこない、というわけです。そして、結果的に自分でマネジメントするようになるという理論を、占領統治においてうまく応用していたのです。
――今村均は、なぜそのような自律統治を目指したのでしょうか。
菊澤 今村均が民族「自立統治」を強く推進した背景には、第一次大戦後のパリ講和会議に参加し、白人と有色人種の差別を強く感じた体験があります。パリ講和会議において日本は「人種差別撤廃」を掲げる条項案を提案しましたが、米国をはじめ英仏の反対が強く、最終的に採用に至らなかった経験から、「アジアの独立」を強く意識していたのだと考えます。
そこから、「支配」ではなく「アジアの独立」につながる統治を志向したと私はみています。結果として、戦後のオランダとの独立闘争でも日本人が残って協力し、インドネシアの自立へとつながっていきました。
また、最近、日本の政界で話題になっている「保守」という言葉にも関係しています。その思想は、英国の政治家エドマンド・バークに始まるといわれています。彼は、伝統や歴史や習慣を完全に破壊したフランス革命を批判し、歴史や伝統を維持しつつその時々の時代に合せて漸次的に修正すべきだと主張しました。この保守の思想を経営学に導入したのが、マネジメントの父、ピーター・ドラッカーであり、まさに保守のマネジメントを軍政に取り入れたのが今村均といってもいいと思います。
今村均と富士フイルムに学ぶ「自律と再構成」
――著書では、今村均のジャワ軍政の事例について、2000年代初頭に経営危機を乗り越えた富士フイルムのケースに似ている、と述べています。富士フイルムの変革においては、どのような点でダイナミック・ケイパビリティが発揮されたのでしょうか。
菊澤 富士フイルムは、デジタル化の大きな流れの中で危機に直面した企業の一つです。一般的には、危機的状況では強いリーダーシップのもと、権限を一極集中させて革命的に変革を起こしていかなくてはいけない、と考えるでしょう。
ところが当時、社長・CEOを務めた古森重隆氏(現・富士フイルムホールディングス最高顧問)は、自身で描いた理想やビジョンをそのまま強制的に現場に実行させる、という革命的な方法を取りませんでした。
むしろ、各人から既存の技術や知識に基づいて「面白いアイデアはないか?」「今ある資源を応用できないか?」とアイデアを引き出し、少しでも芽が出れば事業化を推進させ、その責任は社長が取る、という分権化の経営、あるいは保守のマネジメントを徹底しました。
こうした経営手法について、海外では「富士フイルムは革命的にデジタル化を進めた」と評されることもありましたが、それは実態とは異なります。同氏が行ったことは、ダイナミック・ケイパビリティを発揮して伝統的な知的資源を再構築すること、つまり保守のマネジメントのもとに多角化を行っていったのです。その一つが、フィルムの乾燥を防ぐための材料であったコラーゲンの技術を使って、化粧品事業に打って出るというものでした。
さらに、伝統的な技術や知識を応用してサプリメント市場や再生医療へと次々に多角化を進めました。既存の知識や伝統的な技術の自由な組み替えによって、新規事業の創出に成功したのです。ゼロから革命的に創造したものではないのです。
これは、変化を感知し機会をとらえ、事業モデルを再構築したダイナミック・ケイパビリティの好事例です。その要となっていたのは、「危機には強いリーダーシップによる強権集中」という急進的なマネジメントではなく、これまでの伝統や歴史を継承しつつ分権によって現場の力を引き出し、良いものを見いだして育てる創造的保守の姿勢だったことが分かります。