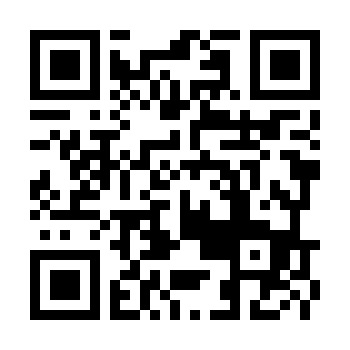(出所:GM PRESSROOM)
(出所:GM PRESSROOM)
中国自動車産業が台頭する一方で、そもそも国外展開にそれほど積極的ではないアメリカの自動車は、日本ではすっかり存在感が薄くなっている。しかしアメリカは今も世界第2位の自動車生産・消費国であり、日本の自動車メーカーにとっては重要な市場であり続けている。トヨタ、フォルクスワーゲングループに次ぐ規模を誇るGMを筆頭に堅調な成長を続けるアメリカの自動車産業の現在を自動車ライター・大谷達也氏が解説する。
自動車メーカーにとっては「おいしい市場」
以前リポートしたとおり、現在、世界最大の自動車生産国かつ自動車消費国は中国であり、かつて栄華を誇ったアメリカ合衆国(以下、アメリカ)はどちらも世界第2位の地位に甘んじている。しかも、その差は大きく、四輪車生産台数でいうと中国の3000万台あまりに対してアメリカは約1000万台、販売台数も中国のおよそ3000万台に対してアメリカは1600万台ほどとなっている。
それでも、アメリカがいまも重要な自動車市場の一つであることに変わりはない。
そのことを端的に示しているのが両国の新車平均価格で、中国の350万円ほどに対してアメリカはおよそ670万円と、倍近い開きがある。裏を返せば、中国よりもアメリカの方が1台あたりの利益が大きく、自動車メーカーにとっては「おいしい市場」といえるだろう。
事実、フェラーリ、ランボルギーニ、アストンマーティンといった超高級車メーカーにとって最大の市場はいずれもアメリカで、この点では依然としてナンバー1の地位を保っている。
トラック人気も相変わらず
その他にもアメリカ市場には興味深い傾向がある。広い室内空間と高い運搬力・走破性を誇る大型の乗用トラックであるピックアップトラック(以下、ピックアップ)やSUVの人気が極めて高いのだ。
 アメリカ車の代表とも言える「フォード F-150」(左)、そのEV仕様のF-150 Lightning(右)。中央は「スーパーデューティー」と呼ばれるシリーズ(出所:FORD NEWSROOM)
アメリカ車の代表とも言える「フォード F-150」(左)、そのEV仕様のF-150 Lightning(右)。中央は「スーパーデューティー」と呼ばれるシリーズ(出所:FORD NEWSROOM)
例えば、2023年にアメリカで最も多く売れた自動車はフォードのFシリーズと呼ばれるピックアップで約75万台。2位はシボレー・シルバラードの約56万台、3位はラム・ピックアップの44万台で、いずれもキャビンの後方に屋根のない荷台を備えたピックアップばかり。それも全長は5m以上、全幅は2.2m以上と、日本やヨーロッパでは考えられないほど巨大なサイズとなっている。
ちなみに、こうした傾向は昨日、今日始まったものではなく、フォード・Fシリーズの中でも代表作とされるF150は40年以上にわたりアメリカでベストセラーの座に君臨してきた。まさにピックアップはアメリカ人の生活に密着した存在といっていいだろう。
 かつて1分に1台売れると言われたこともある「シボレー シルバラード」のEVモデル「シルバラードEV RST」(出所:GM PRESSROOM)
かつて1分に1台売れると言われたこともある「シボレー シルバラード」のEVモデル「シルバラードEV RST」(出所:GM PRESSROOM)
そして4位以下にはトヨタRAV4(約43万台)、テスラ・モデルY(約40万台)、ホンダCR-V(36万台)とSUVが続く。なお、ボディタイプ別の販売台数でいうと、SUVが880万台ほどと一番多く、次にセダンなどの乗用車(約323万台)、ピックアップ(約286万台)、そしてミニバン/フルサイズバン(約73万台)となっている。
 Tesla Model Y(出所:Tesla)
Tesla Model Y(出所:Tesla)
いずれにしても、日本やヨーロッパに比べると外寸の大きなクルマが好評なことは間違いない。これは、そもそもアメリカの国土が広く、道幅も広ければ平均的な移動距離も長いことに加え、ガソリンの平均価格が1リッター当たり130円ほどと割安であることも関係しているはずである。ちなみに、現在、日本ではレギュラーガソリンの平均価格がおよそ175円。これがドイツになると1リッターあたり2ユーロ前後、つまり300円を優に超えている。なお、アメリカのガソリン価格が安いのは、同国が世界最大の産油国であることと深い関係があると思われる。
日系自動車メーカーが米国で確固たる地位を築けた理由
ここでアメリカ市場における自動車メーカー別の販売台数(乗用車と小型トラックの合計)を見ると、トップはGM(ゼネラルモーターズ)で257万7662台、2位はトヨタで224万8477台、3位はフォードで198万1332台、4位はステランティスで155万34787台、5位はホンダで130万8186台、第6位は日産で89万8796台となっている(2023年の統計)。
 北米トヨタのフルサイズピックアップトラック「タンドラ」(出所:Toyota USA Newsroom)
北米トヨタのフルサイズピックアップトラック「タンドラ」(出所:Toyota USA Newsroom)
このうち海外資本系ではトヨタの活躍が目立つが、トップ5の中で唯一、大型のピックアップを持たないホンダが5位にランクインしている点も注目される。なお、トヨタ、ホンダ、日産などの日系自動車メーカーは1980年代に緊迫化した日米貿易摩擦の影響を受けて現地生産化が進んだことも、アメリカで確固たる地位を築いた一因といえる。
ちなみに、ステランティスはプジョーやシトロエンなどを傘下に収めていたグループPSAとフィアット・クライスラー・オートモビルズが2021年に合併して誕生した他国籍企業だが、アメリカ自動車メーカーのビッグスリーとして数え上げられたかつてのクライスラーが属していることからアメリカ市場では伝統的に一定のシェアを獲得している。現在、ステランティスに属するアメリカ系自動車ブランドとしてはクライスラーの他にジープ、ラム、ダッジなどが挙げられる。
 ダッジ「デュランゴ」このモデルに搭載されている半球形の燃焼室を持つ「HEMI」はアイコニックなV8エンジン(出所:Stellantis Media)
ダッジ「デュランゴ」このモデルに搭載されている半球形の燃焼室を持つ「HEMI」はアイコニックなV8エンジン(出所:Stellantis Media)
首位のGMの強固な黒字体質
アメリカ市場で最も販売台数が多いGMは1908年の設立。その目的は、複数の自動車ブランドを保有する持ち株会社となることだったが、設立時点でビュイックとオールズモビルを傘下に収めていた他、翌年にはフォードさえ買収寸前まで交渉が進んでいたというのだから驚く(フォード買収は資金繰りの目処が立たずに頓挫)。その後も高級車ブランドのキャデラック、大衆車やスポーツモデルと得意とするシボレーなどを獲得。1930年代以降は世界最大の自動車メーカーとして君臨し続け、その座を2008年まで77年間にわたって守ったとされる。さらには2017年までは年間販売台数900万台前後を維持し続けてきたが、2018年以降は次第に下降。2020年以降は600万台前後で推移している。
GMの事情に詳しい関係者は、その理由が「台数主義から利益重視主義への転換」にあったという。例えば2024年上半期の決算で比較すると、販売台数と売上高はGMが278万台/910億ドル、最大のライバルであるフォードが219万台/906億ドルで大差ないのに対し、利益の指標の一つであるEBIT(利払前・税引前利益)はGMが93億ドル、フォードは55億ドル。営業利益率で見るとGMの9.1%に対してフォードは6.1%と大きな開きがある。
フォードの利益を圧迫している要素として、EV事業の損失が大きいことがよく指摘される。事実、2024年上半期にフォードのモデルeと呼ばれるEV事業は3万6000台を販売して24億6300万ドルという巨額の赤字(EBIT)を計上している。一方のGMは、パワートレイン別の収支は公表していないものの、同じ2024年上半期に3万8000台以上のEVを販売した。こうした統計を見てもGMの利益体質が強固であることが分かる。
前出の関係者によれば、GMのビジネスが好調なのは利益率の高い内燃エンジン搭載の大型SUV/ピックアップや中型SUV/ピックアップのセールスが好調なことに大きな要因があるという。言い換えれば、アメリカ経済の長期的な成長とアメリカ市場を重視した製品戦略が、GMの成功を下支えしているとも考えられるのだ。
 2024年12月、GMが25周年を迎えて2百万台を販売したとニュースを発表したGMCブランドの高級グレード「デナリ」。写真は最新のフルサイズSUV「ユーコン デナリ」(出所:GM PRESSROOM)
2024年12月、GMが25周年を迎えて2百万台を販売したとニュースを発表したGMCブランドの高級グレード「デナリ」。写真は最新のフルサイズSUV「ユーコン デナリ」(出所:GM PRESSROOM)
一方でGMは自動車の将来技術開発にも積極的に取り組んでいる。彼らは「ゼロクラッシュ、ゼロエミッション、ゼロコンジェスション」、つまり事故、CO2排出量、交通渋滞のいずれもゼロにすることを目標として掲げていて、これを総称して「トリプルゼロ」と呼んでいる。これらは現代の自動車メーカーが必ず向き合わなければいけない課題とはいえ、そうした努力を強固な黒字体質の下で実現している点にGMの大きな特徴がある。今後、中国車メーカーの台頭が予想される中、収益性を確保しながら技術競争を勝ち抜いていく姿勢は、既存の自動車メーカーにとってさらに重要となるだろう。
 GMはEV充電インフラ企業と提携し米国内に充電ステーションを拡大している(出所:GM PRESSROOM)
GMはEV充電インフラ企業と提携し米国内に充電ステーションを拡大している(出所:GM PRESSROOM)
GMの経営にもしもリスクがあるとすれば、それは利益の大半をアメリカ市場に依存している点にある。ただし、アメリカ経済が長期にわたり安定的に成長し続けている事実に目を向ければ、これも当面はデメリットというよりメリットでしかないように思える。一般的には世界経済に対する不安材料と見なされている次期トランプ政権の影響に関しても、彼らが自国産業の保護を掲げている以上は、GMに代表されるアメリカ自動車産業への懸念材料とは言い切れない。
強固な経済を基盤として独自の文化を育んできたアメリカの自動車市場と自動車産業。その未来に、深刻な懸念材料は今のところ見当たらないといえそうだ。