 Baka Sobaka/Shutterstock.com
Baka Sobaka/Shutterstock.com
大企業の経営幹部たちが学び始め、ビジネスパーソンの間で注目が高まるリベラルアーツ(教養)。グローバル化やデジタル化が進み、変化のスピードと複雑性が増す世界で起こるさまざまな事柄に対処するために、歴史や哲学なども踏まえた本質的な判断がリーダーに必要とされている。
本連載では、『世界のエリートが学んでいる教養書 必読100冊を1冊にまとめてみた』(KADOKAWA)の著書があるマーケティング戦略コンサルタント、ビジネス書作家の永井孝尚氏が、西洋哲学からエンジニアリングまで幅広い分野の教養について、日々のビジネスと関連付けて解説する。
連載第3、4回は、実は多くの人が勘違いしているヘーゲルの「弁証法」について前後編の2回にわたってお届けする。
ヘーゲル哲学は「正反合」ではない
ビジネスパーソンが骨太なビジネス思考を身につける上で役立つ実践的な教養を学ぶための本連載、第3回目はヘーゲル哲学を取り上げる。
ちまたでは「ヘーゲル哲学は、正反合でアウフヘーベン」と説明する人が多い。高校の倫理の教科書でも、「ヘーゲル哲学は正反合を通して、真理を明らかにする」とある。『広辞苑』によると「アウフヘーベン=止揚、揚棄。ヘーゲル哲学(弁証法)の用語」とある。有名な知識人でも「ヘーゲル哲学=正反合」と解説する人は少なくない。こんな説明をする人もいる。
「『正』の意見に『反』の意見をぶつけてアウフヘーベンして、『合』という解決策を目指す。A君は『カレーを食べたい』(正)。B君は『トンカツを食べたい』(反)。アウフヘーベンして『カツカレー』(合)にすれば、二人とも満足。これがヘーゲル哲学の弁証法だ』
これらは全てヘーゲル哲学の勘違いだ。ヘーゲルは「正反合」なんてひと言も言っていない。
ヘーゲル哲学が誤解される理由の一つは、主著書である『精神現象学』が難解で、読みこなしている人が少ないためだ。(後述するが、もう一つ理由がある)。
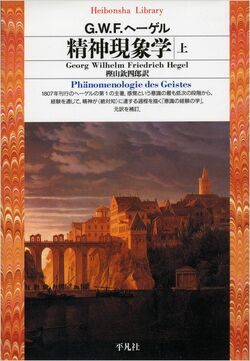 『精神現象学(上・下)』(G.W.F.ヘーゲル著、樫山欽四郎訳、平凡社ライブラリー)
『精神現象学(上・下)』(G.W.F.ヘーゲル著、樫山欽四郎訳、平凡社ライブラリー)
ヘーゲルの著書を熟読する日本の哲学研究者には、「ヘーゲル哲学は正反合」と言う人はいない。「ヘーゲル=正反合」と説明するか否かは、ヘーゲル哲学の理解度を判定する上でのリトマス試験紙なのだ。
「そんなに難しいなら学んでも意味ないじゃない?」と思うかもしれないが、ヘーゲル哲学が分かれば、これまで見えなかったことが見えてくる。難解だが挑戦しがいもある。それがヘーゲル哲学なのだ。そこで今回は前編と後編に分けて、ヘーゲル哲学を取り上げたい。
『精神現象学』は邦訳が多いが、ここでは早稲田大学哲学科の樫山欽四郎教授による1973年の邦訳『精神現象学(上・下)』(樫山欽四郎訳、平凡社ライブラリー)を取り上げ、解説書も援用しつつ、ヘーゲル哲学について理解を深めていこう。
ヘーゲル弁証法の本質は「否定」である
ヘーゲルは『精神現象学』の序論で、弁証法的な構造の例え話として植物が育つ過程を紹介している。つぼみから花が咲き、花が散って果実がみのり、また種が芽を出すプロセスを、次のように表現している。
「つぼみは、花が咲くと消えてしまう。そこで、つぼみは花によって否定されると言うこともできよう。同じように、果実によって花は植物の偽なる定在と宣告され、その結果植物の真として果実が花に代って登場することになる」
これがヘーゲルの素の文章だ。この文章が900ページ続く。
「『つぼみが咲いて果実になる』でいいじゃん。なんでわざわざ『つぼみが花で否定される』なの?」と言いたくなるが、これは「否定の力」を強調するためだ。そして種は、再び種に戻る。
「否定に否定を重ねて再び種に戻るように、モノゴトにはひとまとまりの過程がある」ということを、この例え話で表現している。この弁証法的な構造のどこにも「正反合」はない。弁証法のカギは「否定の力」なのだ。
「否定の力」は、人間社会の中でこそ真価を発揮する。私の場合、本の執筆がまさにそうだ。
手間と労力をかけて書いた自信満々の原稿が、編集者にダメ出しされることがよくある。正直に告白するとこんな時は、最初はなかなか受け入れられない。編集者と徹底議論しても納得できない。しかしやがて「ココがダメだったのか」と気付く。同時に編集者の意見を超える案も思いつく。こうして双方の否定の末に、レベルが格段にアップした原稿ができる。執筆ではこれが延々と繰り返される。
 『成功はゴミ箱の中に』(レイ・クロック、ロバート・アンダーソン著、野崎稚恵訳、プレジデント社)
『成功はゴミ箱の中に』(レイ・クロック、ロバート・アンダーソン著、野崎稚恵訳、プレジデント社)
マクドナルド創業者のレイ・クロックは、著書『成功はゴミ箱の中に』(プレジデント社)の冒頭で座右の銘を書いている。「未熟でいるうちは成長できる。成熟した途端、腐敗が始まる」。この言葉は「未熟だと自分を否定しやすいが、成熟すると否定が難しい」と受け止めるべきだろう。
ヘーゲルは『精神現象学』でこう述べている。
「以上のような弁証法的運動は、意識にとって新しい真の対象がそこから生れてくる限りで、意識が自分自身において、自らの知と自らの対象において、行う運動であり、本来は経験と呼ばれるものである」
独特の“ヘーゲル語”なので解説すると、「経験」とはヘーゲル語で「自分は間違っていた、と気付く経験」のことだ。つまりヘーゲルはこう言っている。
「自分は知っているつもりでも、間違えることも多いもの。『自分が間違い』という気付きを得れば、自分が正しいと考える知のあり方や世界の捉え方も、変わってきますよ」
なぜ日本では誤解されているのか?
このようにヘーゲルの弁証法では、自分も相手も全身全霊で否定する。そこから新たな知を紡ぎ出す。こう考えると、「ヘーゲルの弁証法は、正反合でアウフヘーベン」という説明は、本来のヘーゲルの弁証法とは似ても似つかないシロモノと分かる。
カツカレーの例では、A君もB君も本気で否定していない。両方にいい顔をした、安易ないいとこ取りだ。カツカレーが出ても、カレーを食べたいA君は『肉は苦手…』、トンカツを食べたいB君は『カレーは辛くてなんか嫌…』と思うかもしれない。本音の対話をしなかった結果だ。双方否定するヘーゲルの弁証法とは、似ても似つかない。
なぜこんな誤解が生まれたのか? 『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)の「正反合」の項目に経緯が書かれている。
 『新しいヘーゲル』(長谷川宏著、講談社現代新書)
『新しいヘーゲル』(長谷川宏著、講談社現代新書)
「正・反・合・・・ドイツ語のテーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼの訳語である定立、反定立、総合を略したもの。フィヒテが『全知識学の基礎』(1794)で用いた概念であるが、マルクスやイギリスのヘーゲル学派がこの概念を借用して、ヘーゲルの弁証法を通俗的に説明したところ、日本にヘーゲル哲学が紹介されたとき、誤ってヘーゲルそのものが用いた概念であるかのように解され、日本では、そのままほぼ定着している。(中略)『正・反・合』をヘーゲルの概念であると誤解した場合に生ずる内容上のずれは、ヘーゲルの弁証法が著しく『総合』に重点を置くもののように解される点にある」
つまり広辞苑や高校の教科書が間違っている。ヘーゲルを研究してきた在野の哲学研究者であり、ヘーゲルを中心に海外哲学者の翻訳も多く手がけている長谷川宏氏は、著書『新しいヘーゲル』(講談社現代新書)でこう述べている。
「図式的説明としてよく援用される正‐反‐合の三段階に即していえば、社会の動きの全体が最終的に『合』に帰着することに安堵を覚える。が、みずからの生活実感にもとづくそうしたヘーゲル理解は、まったく的を外している」
ということで、今日からは「ヘーゲル弁証法は正反合」と言うのはやめましょう。
ところでここで疑問が出てくる。ヘーゲルは本書で何を言いたかったのだろう? これについては後編で紹介したい。


