 INCJ代表取締役会長兼CEOの志賀俊之氏(撮影:今祥雄)
INCJ代表取締役会長兼CEOの志賀俊之氏(撮影:今祥雄)
日産自動車COO、武田薬品工業の社外取締役などを務めた志賀俊之氏は現在、官民ファンドの会長兼CEOとして次世代の産業を担う企業に対して投資の面から支援を行っている。インタビュー後編は、志賀氏がさまざまな経営者との対話、取締役会の経験から得た、日本企業が成長するためのリーダーシップ、執行チームと社外取締役との最適な関係性などを語る。
「秘蔵っ子社長」では大胆な経営はできない
――前回は、日本企業の競争力低下の理由、スタートアップを取り巻く課題などに触れました。今回は、経営者の資質、取締役会のあり方などをテーマにしたいと思います。まず、日本の企業経営者は任期が短く、思い切った改革ができないという意見があります。それについてどうお考えですか。
 志賀 俊之/INCJ代表取締役会長兼CEO
志賀 俊之/INCJ代表取締役会長兼CEO1976年日産自動車に入社。1999年ルノーとのアライアンス締結に関わり、企画室長及びアライアンス推進室長を兼務。現場とのパイプ役として、日産リバイバルプランの立案・実行に参画し、2000年46歳で常務執行役員に抜擢される。2005年4月から2013年11月代表取締役副会長に就任するまで、最高執行責任者(COO)を務める。2015年6月官民ファンドである産業革新機構(現INCJ)代表取締役会長に就任。
志賀俊之氏(以下・敬称略) 任期の短さも問題ですが、それ以前に、これまでの大企業の社長への道筋が良くないと思います。
日本には、世界で戦っていける素晴らしい企業経営者がいらっしゃいます。ソフトバンクの孫さん、ファーストリテイリングの柳井さんなど現役のトップ以外にも、たくさんの優れた経営者がいますが、ほぼ全員が創業者です。
私は、ずっとサラリーマンをしてきてつくづく思うのですが、サラリーマンで社長になる人は、「じゃんけん」に勝ち続けてきた人なのです。つまり、キャリアの中でたった一度も、失敗をしたことがない人です。1回でも失敗をすると、日本企業の場合はそこで出世の道が途絶えてしまいます。
シリコンバレーは失敗を許す文化であり、日本企業のベンチャーキャピタルは総じてやや冷たい、という話をしましたが(前編を参照)、企業内にもそれと同じ構図があります。新事業で失敗する、部下の不祥事の責任を取る、といったことがあると出世する道が途絶えてしまいます。
そういう文化があるため、私の世代の優秀な人たちは「秘蔵っ子」でした。絶対に失敗しない安全な道を歩かせて、上に上げていくという仕組みが会社の中にできていたのです。もちろん、雑草のように下から這い上がってきた経営者もいますが、数的にはごくわずかです。
秘蔵っ子の問題点は、経営者としてのリーダーシップを一切学んでいないことです。リーダーシップを発揮できないため、重要な局面で意思決定することができません。ソフトバンクは過去にArm(アーム)という半導体メーカーを約3兆円で買収しましたが、孫さんは、取締役会で買収を提案したときに、「誰一人自分の意見を理解してくれなかったが押し通した」と話しています。経営者はときには、そういう行動ができなければ、世界で勝てる企業にはなれません。
上に忖度し、ご機嫌を取りながら安全に階段を上がっていくという、日本の伝統的な企業文化を変えていかなければ、優秀な人材ほど失望して、会社を去っていきます。事実、そうした人材がスタートアップの人材市場に流れていて、スタートアップ企業が元気になっているという話も聞きます。
労務費のカットが日本企業の成長力を奪った
――その状況を変えるには、経営者の世代交代しかないのでしょうか。
志賀 そうですね。私も含めて、新しい世代を後ろから応援するような体制をとるべきだなと、本当は思っています。
私の世代の経営者の間に、多くはびこっている共通言語があります。それは「コストカット」「リストラ」「人件費」です。私自身の反省でもありますが、コストの中の労務費をどれだけそぎ落としたかを競い合っていた時代がありました。
しかし、それで日本企業はおかしくなってしまったところがあります。私が若手社員だった時代の大企業にはいろいろな研修制度があり、社員を選抜して社費で海外留学をさせていました。しかし現在、そんなことをしている企業はほとんどなくなってしまいました。今、表面上「人的資本経営」といっていますが、昔と比べて、確実に人的投資は減っています。
しかし光明もあります。人件費を減らして短期的な利益を出していた経営者に対して反発しつつも、会社を辞めずに上の様子を反面教師にして、自分の代で変えてやろうとがんばる人も現れています。大いに期待したいと思っています。
社外取締役は、スキルマトリクスで選ぶべき
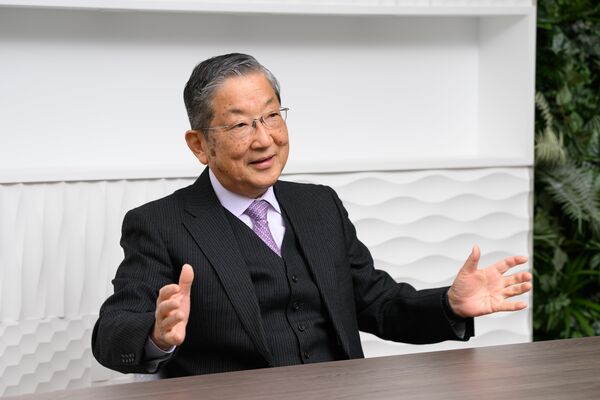
――話を取締役会、社外取締役の在り方に移したいのですが、特に社外取締役は、本来社内では得られない角度の見方を提供する役目を果たすことが求められていると思います。その機能は十分に果たされていると思いますか。
志賀 私もこれまで武田薬品工業などの大企業で社外取締役を務めたことがありました。一方で、現在のファンドで部下だった人が興したスタートアップの社外取締役も務めています。比べてみると、立場は全然違います。
大企業では、執行体制が出来上がっている状態で、必要なコーポレートガバナンスを果たすために、社外取締役を置くことが、ある意味で目的の1つです。そのため、いろいろと口を挟むことは疎まれる傾向があります。「"社外”がうるさいから、資料を具合のいいように作っておいて」といった指示が出ることも多いようです。
場合によっては、わざと社外取締役に突っ込ませる「重箱の隅」を作っておいて、その餌に食いつかせておいてガス抜きして提案自体は通そうという駆け引きをする執行チームもあると聞きます。そんなことを繰り返しても、いいはずがありません。「ガバナンスを敷いているポーズ」からの転換が、今問われていると思います。
――では、企業はどうやって社外取締役を選んで、経営に生かせばよいのでしょうか。
志賀 スタートアップの社外取締役をやっていて分かったのですが、執行チームは経験も浅く、社外取締役にも率直に質問をしてきます。そういった質問には私たちも、自分たちで助言できることは言いますし、場合によってはメンタリング的に背中を押すこともあります。本来、社外取締役は、口を挟むとか、ああしろ、こうしろという役割ではなく、「一緒に考える」ことが会社のためになるということです。
大企業でも、執行チームのスキルマトリクスを作ってみて、弱いところを割り出し、それを補うような人材を社外取締役に選ぶという方法があります。グローバル経験がない、法律や会計に不安があるといった弱点をカバーするスキルを持った人材に入ってもらい、一緒になって考える。それが本来の取締役会の在り方だと思います。
――社外取締役を含め取締役会をうまく機能させて、成長した企業はあるのでしょうか。
志賀 数年前に経済同友会の経営効率最適化委員会(当時の名称)で、「伊藤レポート」(経済産業省による企業経営に関するプロジェクトの報告書)を受けて企業のROEをどうやって高めるかを議論していました。何社かの経営者を招いて取締役会の機能と執行の結びつきなどをヒアリングして、ベンチマークしました。
その時にお話を聞いた企業の1社が、オムロンでした。当時の山田義仁社長の下で、資本効率を重視した独自のROIC経営を実践していました。詳細は省きますが、要は株主から預かった資本を使って、事業で最大のリターンを稼ぐために、経営から現場までが意識をそろえて一気通貫で進めています。
しかも当時の山田社長は、自らの任期の間は毎年指名委員会で選任されなければ退任する仕組みを実践していました。ビジョンは長期で持ちながら、毎年、「今年はこれをやります」という目標を決め、1年後にそのマイルストーン達成に自分の進退を賭けるということを10年以上続けたのです。日本企業の社長の多くが、成果によらず4、5年の任期を務めるなかで、オムロンの経営者の意識と取締役会の関係性は群を抜いており、私は日本企業のガバナンス変革の代表例だと思っています。
企業は「箱」なく、「人の集合体」だと再認識する
――日本企業の競争力を取り戻すために、取締役会、ガバナンスをどう変えていけばいいのでしょうか。
志賀 一般的に企業価値とは、株価×株数のような形で計られることが多いですが、本当はそうではありません。一人一人の従業員の価値のシグマ(総和)によって価値は決まると、私は昔からみなさんに話しています。
企業は、何かの数字が詰まった、ただの「箱」ではないのです。従業員一人一人が成長することで、パフォーマンスを発揮して、結果として企業価値が上がります。しっかりと人に対する投資を続けなければ、企業は成長できません。これが今、非常に重要になっています。
先日、トヨタ自動車の豊田章男会長が「グループビジョン」の説明会を行いました。ダイハツ工業などの不正が問題となっているさなかで、豊田会長が話したのは「原点回帰」でした。
一連の不正を受けて、豊田会長は悩まれたと思います。その末に出されたのが、「現場を大切にしたい」という思いだったように感じました。だから、経営効率の指標改善などという前に、現場の声を聞いて回って、もう一度トヨタの進むべき道を見つけるという宣言をしたのだと思います。
――経営のリーダーシップも大事だけど、従業員の声も聞いて、行きすぎを抑える役割を、取締役会は持たなければいけないということでしょうか。
志賀 トップが強すぎると、行き過ぎたり暴走したりした時にブレーキをかけられなくなります。日産時代のカルロス・ゴーン氏は、「ストレッチターゲット」と言っていましたが、あり得ないような高い目標を示して、「それをやれ」と言っていました。しかし「これは無理です」という人は誰もいないまま、現場に降りていきました。
ストレッチですから、つま先立ちで精一杯背伸びしているわけですが、それでも現場は必死にがんばってしまいます。そうすると、現場が無理をしているという状況が上に上がらず、トップは無理を強いているということを感じません。その結果、いろいろなゆがみ、問題が起きてくることになります。
企業価値の向上において、経営層の決定によって現場がどうなっているか、つま先立ちになっていないかを見るということは経営の原点です。だからこそ、そこに立ち返るというトヨタの決定は素晴らしいと思ったわけです。
会社を引っ張っていく強いリーダーシップ型の経営を志向する経営者が多かった時代もありました。しかし今は、現場を盛り上げて会社を強くしていく「サーバントリーダーシップ」のスタイルにシフトし始めています。私もそこに共感しており、現場の声を聞き、経営に生かしていく取締役会であってほしいと願っています。



