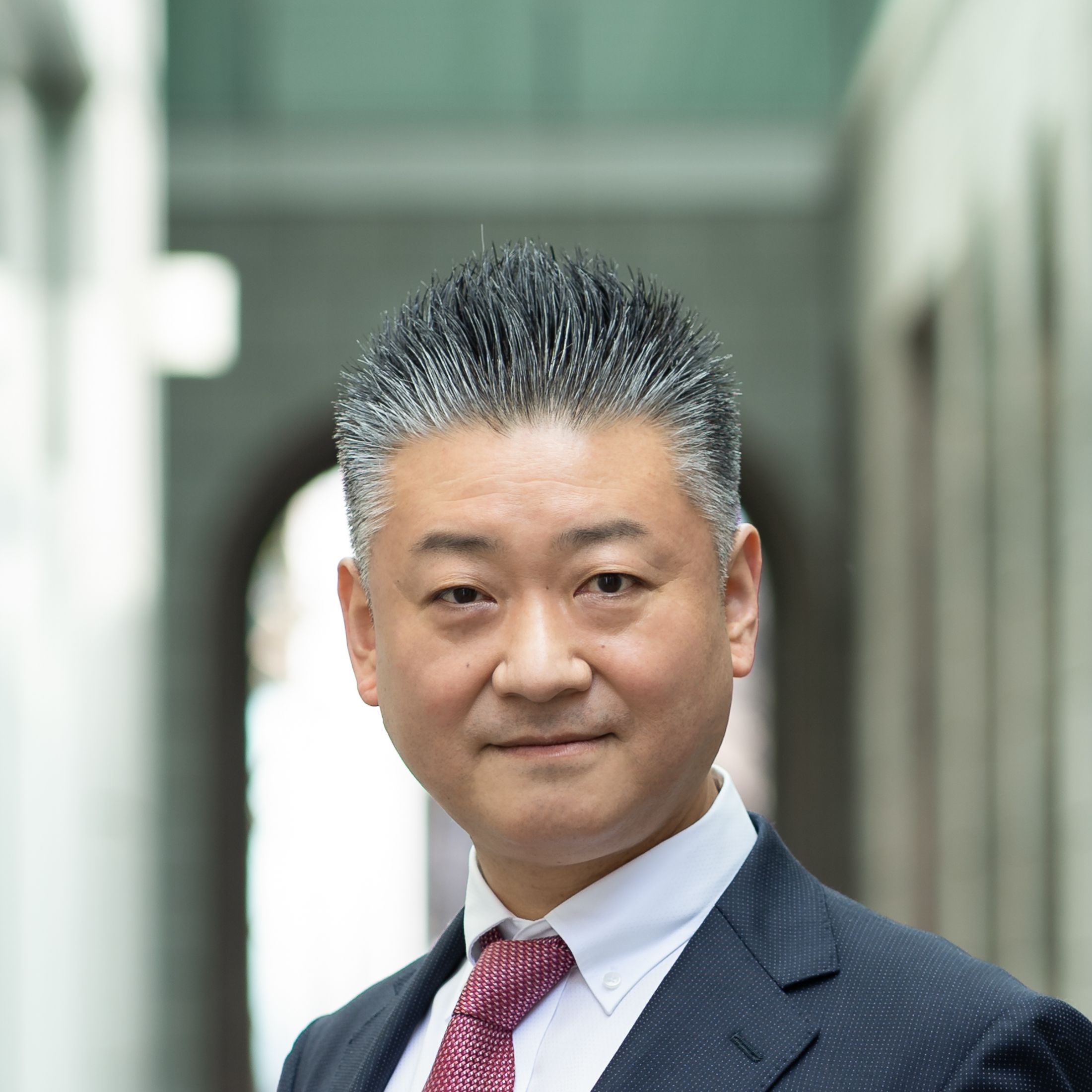1969年、「お茶づけ海苔」のPRイベントとして、東京のアメ屋横丁(アメ横)で行われた「お茶づけ祭」。アメ横で店を構える各商店の協力を得て実施された「お茶づけ祭」には、買い物客、見物人をはじめ、多くの人が足を止めたという
1969年、「お茶づけ海苔」のPRイベントとして、東京のアメ屋横丁(アメ横)で行われた「お茶づけ祭」。アメ横で店を構える各商店の協力を得て実施された「お茶づけ祭」には、買い物客、見物人をはじめ、多くの人が足を止めたという
●永谷園の強さの理由に迫るシリーズ第1回はこちら!
「お茶づけ海苔」にスポットを当てた前回(連載2回目)。永谷園が企業として創業するまでを振り返りつつ、「お茶づけ海苔」が誕生するまでの経緯などを紹介した。また、「お茶づけ海苔」が誕生したストーリーに加え、“変えない・変わらない”という永谷園の強さ、ヒット商品の誕生には時代の背景とタイミングをつかむことが重要になることも述べた。
さて、今回(連載3回目)は、連載の本筋から見れば、少し脇道に逸れるかもしれないが、前回、「お茶づけ海苔」に触れたことを踏まえ、その延長線上の話として、お茶漬けの素に対する永谷園の強いこだわり、先見的な視野と開発力、そうしたエピソードについても記したいと思う。
品質を求め、海苔に課した3つの条件
では、早速、本題に入ろう。永谷園の定式幕を模したお茶漬けの素には「お茶づけ海苔」をはじめ、「さけ茶づけ」「梅干茶づけ」「わさび茶づけ」「たらこ茶づけ」など、おなじみの商品が顔をそろえる。そして、これらの商品には一見して、共通したものが入っている。それは、あられと海苔だ。
 「お茶づけ海苔」「さけ茶づけ」など、おなじみの商品が並ぶ。今年は「お茶づけ海苔」が発売70年、「梅干茶づけ」が発売50年と、周年を迎えている
「お茶づけ海苔」「さけ茶づけ」など、おなじみの商品が並ぶ。今年は「お茶づけ海苔」が発売70年、「梅干茶づけ」が発売50年と、周年を迎えている
茶碗に装ったご飯に、お茶漬けの素をササッと振りかける。そして、お湯を注ぎ、アツアツのお茶漬けを啜る。そんなシーンでさえ、以前の私がそうであったように、ほとんどの人が「あられや海苔が入っているなぁ」といった程度の意識で、取り立てて、あられや海苔に気を留めることなく、お茶漬けを啜ってきたことだろう。
しかし、ごく自然に、当たり前のように入れられている海苔。多くの人が気に留めることがない“あの刻み海苔”にも、永谷園は強いこだわりを持っている。
では、永谷園の海苔に対するこだわりとは、どのようなものだろうか。
お茶漬けのスタンダードな食べ方として、お茶漬けの素を利用した場合、お湯を注いで食べることになるわけだが、お湯をかけると、どうしても海苔は溶けやすくなる。風味が豊かで、デリケートな食材でもある海苔。そんな食材だからこそ、永谷園は海苔にこだわっている。
1952年に「お茶づけ海苔」を発売した後、永谷園の商売は大きく軌道に乗り始める。すると、茶屋、工場、事務所、住居を兼ねていた東京・芝愛宕町の社屋は手狭になってしまう。そこで、工場を新設することになるのだが、工場建設の地として選ばれたのが、東京・大田区の大森だった。かつて大森は海苔の養殖が盛んで、海苔の本場といわれた。そのことが大森に工場を建設する決め手になったという。この話も「お茶づけ海苔」を発売した当初から永谷園が海苔にこだわっていたことを示すエピソードといえる。しかし、こんな話は序章にしか過ぎない。
永谷園の商品を見ると、お茶漬けの素はもちろんのこと、ふりかけ、お吸いものなど、海苔を使ったものが多い。なので、使用する海苔については、厳しく3つの条件を自ら課している。1つは、焼き色が深緑色で風味がある。2つ目は、お湯をかけても溶けにくい。3つ目は、硬くて重量がある。この3つの条件を永谷園は頑なに守り続けている。
 海苔はお湯を注ぐと溶けやすい。永谷園ではお湯をかけても溶けにくいなど、厳しい条件を課し、海苔を調達している。その違いは左右の画像を見比べてもらえれば、一目瞭然だ。左が溶けにくい海苔、右が溶けやすい海苔
海苔はお湯を注ぐと溶けやすい。永谷園ではお湯をかけても溶けにくいなど、厳しい条件を課し、海苔を調達している。その違いは左右の画像を見比べてもらえれば、一目瞭然だ。左が溶けにくい海苔、右が溶けやすい海苔
「お茶づけ海苔」を発売してからの草創期、工場があった大森には海苔問屋も多く存在した。そうした海苔問屋に赴き、その場で目利きをしながら条件に合った海苔を調達していた永谷園。しかし、生産量が増えてくると、その手法では条件を満たす海苔の確保が難しくなってしまう。