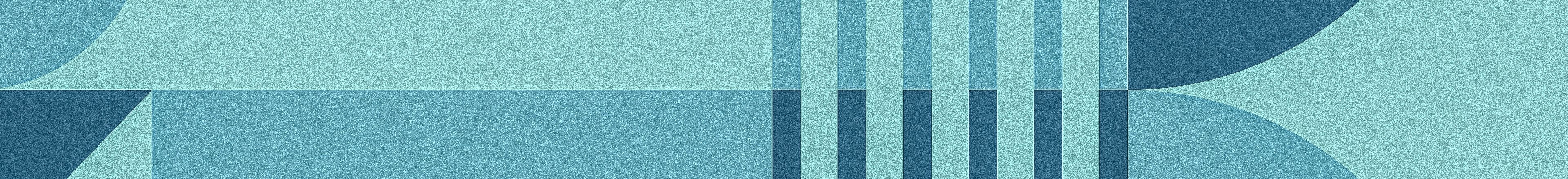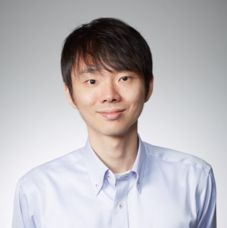前回の記事では、日本企業にフィットしたDX推進の必要性とそれを実現するために不可欠なCXという考え方のほか、組織変革を行うにあたっては、「0→1に向かう新規サービスの立ち上げ」と「1→10に向かうサービスの成長と拡大を担う」という期間があり、それぞれに必要な人材像の特徴などについて取り上げました。
一方で、多くの企業において既に「顧客体験(CX)の再定義」や「新サービスのアイデア構想」への取り組みは活発化しているといった話も聞きます。
むしろ、今まさに課題になっているのは、「どのサービスをどのように開発すれば良いか? どうやって社内を説得してトランスフォーメーションを実現するか?」というフェーズに差し掛かかった時、さまざまな課題にぶつかり、途端に議論が失速してしまうことかもしれません。
では、サービス開発プロジェクトが構想段階で終わらないように、プロジェクト担当者が把握しておきたい進め方とはどのようなものなのでしょうか?
第2回となる今回は、この疑問に対し、「構想フェーズで終わらせない。CXを実現する9つの定石」を、実例を踏まえて解説していきます。
構想と実現の狭間にある壁とは
まずは、サービス開発プロジェクトが構想から次のフェーズに向かう上での課題とはどういったものが挙げられるのか、整理してみましょう。
新規事業を検討する際、ビジネスの成功確率を上げるためにCPF(Customer/Problem Fit:顧客の課題の検証)からSPF(Solution/Product Fit:ソリューションを具体的なプロダクト/サービスとしてデザイン)にかけて、不確実性を取り払う活動を行うのが一般的です。この過程で、全てのアイデアがふるいにかけられ、突破できずに廃案になるものも出てきます。その結果、サービス開発プロジェクト自体が中止になることも多いです。
アイデア自体は玉石混交なので、「実施する/実施しない」と振り分けるのは当然ですが、中には「構想の具体性が薄い」といった理由で日の目を見ない案も出てきます。そうした中にはもしかすると、「過去に例はないものだけど、実は価値ある案だったのに・・・」とか「粗いところに目を瞑ってでもやってみたら大化けするアイデアだったのに・・・」というものもあったのかもしれません。
では、なぜ新規事業のアイデアがアイデアのままで終わってしまうのか? そこには4つの理由が考えられます。
1.経営層、プロジェクトチーム、現場の温度差
組織内にはさまざまな部門・部署があり、ロールによって役割は異なります。置かれている立場の違いによって、あるアイデアに対しての受け止め方や評価の視点は異なるものでもあります。
例えば、経営層は多くの場合、現状の事業課題を主眼としており、新サービスと合致する自社ビジョンや戦略の不在、投資コストや社内マネジメント体制、専門人材などの人材不足について日々課題に感じているもの。一方、プロジェクトを担当するDX推進の実務担当者は、DXに対するサイロ化した組織の中の他部署連携の難しさ、新しい業務プロセスの実行力不足、チャレンジに慣れていない企業文化に課題を感じていると考えられます。
このようにお互いに視座や視野が異なるため、そもそも新規事業に関する議論が成り立ちづらい状況だったことが想像できます。
2.サービスへの期待値に対する認識の差
ビジネスパーソンとして、広い視野を持ち、世の中の動きに敏感になって独自の見通しを立てながら次の一手を考え続けることは、理想的な在り方だと言えます。知の探索と深化のバランスが取れている状態は目指すべきところでしょう。
しかし、日々の業務に追われ、慌ただしく過ごす中で、(1)既存事業に焦点が行きがち、(2)短期的な効果を考えがち、(3)顧客との関係性をピンポイントで捉えがち、(4)既存領域のサービサーを競合と捉えがち、というように、何らかの事柄に捉われて、あるべき認識の上に立てなくなることは往々にして起こるものです。
3.実現性を考慮しない”理想的な体験”をデザインしがち
新規事業の構想だからといって、夢のようなアイデアを出してもいいかと言われると、そんなことはありません。また、例えば、「テクノロジーの力があれば何でもできる!」と言うような現実的ではないアイデアは議論の俎上に載せられないものです。
より具体的に言うなら、システムやデータ先行で考えてしまい、リソースやオペレーションの計画が詰め切れていない、あるいは、新しいドメインにチャレンジする場合のノックアウトファクター(法規制、知的財産、税制度などの観点で突破できない事象)の検討が抜け落ちており、そもそも検討が間違っているケースは、アイデアがアイデアで終わることになりやすいものだと言えるでしょう。
4.体験デザイン後の実装ガバナンスの作り方が分からない
事業創出から事業成長に向かう流れとは、「検証・評価・仮説・検証計画」を繰り返し、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)を特定し、開発計画を立て、スプリント計画を立てて開発をし、レビューをするというプロセスを繰り返してリリースする、というのが基本的な姿です。これを1つのアイデアに対して注力して行えればいいのですが、複数を同時に走らせるケースが多いのが実際のところではないでしょうか。
そうすると、リソース不足や最適人材をアサインできず、「外部から必要なリソースだけを“急ぎ調達する”」ということになってしまい、全体を俯瞰したチーム編成・連携ができなくなることが考えられます。また、目先のタスクで体制を考え、必須タスクの欠落に気づくのが遅くなったり、偏ったメンバーで検討してしまうことも多いので、いざ開発を始める際やリリースする際に他のメンバーとハレーションを起こす事態にもつながりかねません。
大前提として、“開発プロセスにおけるガバナンスは制度として作るべき”だということをしっかりと押さえておかなければ、たとえアイデアが採用されたとしても、構想から実現には至らない、というわけです。
前述のように、アイデアがアイデアのままで終わってしまうのには、それなりの理由があることが分かります。では、幾つもの壁をどのように突破していけばいいのでしょうか?
さあ、ここからはいよいよその答えであり、今回の記事の核心とも言える「CXを実現するための最善の打ち手」について、説明していきましょう。
これまで数々の企業をご支援させていただいた経験から、アイデアのままで終わってしまう壁を抜けるためには、「推進可能な」DXに関わるステークホルダーの巻き込み方、「実現可能な」CXを作っていくためのHow to、そして「実行可能な」専門家のワンチーム体制の構築、の大きく3つが非常に重要なのだと気付かされました。それぞれテーマごとに、あわせて「9つの定石」を紹介します。
なお、この9つの項目には、「何をする必要があるのか」ということだけでなく、「なぜそれをすべきか?」「それをしなければどのような懸念事項が浮上すると考えられるのか?」といった内容も、できる限り詳しく取り上げました。御社内の現段階の状況などを頭に浮かべながら、ぜひ最後まで読み進めていただけばと思います。