文=青野賢一 イラストレーション=ソリマチアキラ
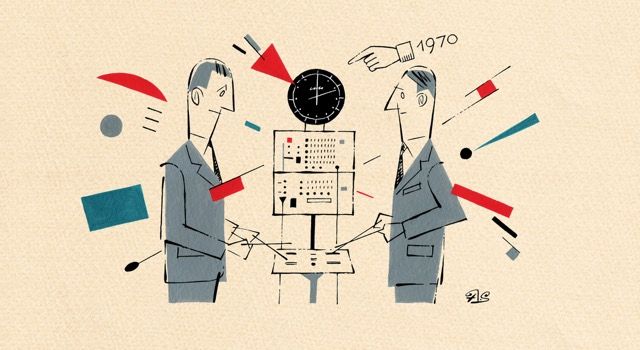
音楽とファッションと、それらにまつわる文化・芸術を語る青野賢一さんによる連載コラム。第1回は、急逝したフローリアン・シュナイダーを偲び、クラフトワークの1970年代にフォーカスします。
この5月に、ドイツのグループ、クラフトワークの創始者の一人であるフローリアン・シュナイダーが亡くなったとの発表があった。訃報は音楽メディアはもとより、一般的なニュースを伝えるサイトでも取り上げられ、また、一時はツイッターのトレンドに上がったことからも、多くの人に影響を与えてきたことをうかがい知れるのではないだろうか。かくいう私も小学生の頃に初めてクラフトワークの音楽を耳にして以来、いまだにDJの際にはレコードバッグにアルバムや12インチ・シングルを入れることも多い。享年73歳。ご冥福をお祈りしたい。
クラフトワークというグループは、先のフローリアン・シュナイダーとラルフ・ヒュッターにより1970年に結成された。二人とも出自はクラシック音楽だが、クラウト・ロックの影響だろうか、クラフトワークはポピュラーミュージックの領域を志向したものであった。初期段階からシンセサイザーなどの電子楽器を導入し、現代のエレクトロニック・ミュージックの祖と仰がれているクラフトワーク。彼らがいなければ、ヒップホップやテクノはもとより、様々なジャンルの音楽のあり方が変わっていたかもしれない。20世紀以降のポピュラーミュージックを考えるうえで、実に重要なグループのひとつなのである。
結成当時のクラフトワークと西ドイツの若者
クラフトワーク結成当時の様子は、YouTubeで公開されている「Kraftwerk live | Rockpalast | 1970」というタイトルのムービーで観ることができる。このライブはフローリアンとラルフ、そしてのちに「ノイ!」を結成することになるクラウス・ディンガーのトリオ編成。実験的なロックという印象であるが、ミニマルな展開がその後のスタイルに引き継がれていることがわかる。
ルックス面でいうと、クラフトワークと聞いて多くの人がイメージする、ラフ・シモンズが1998-99年秋冬コレクションで引用したあの赤いシャツに黒いタイ––––1978年のアルバム『The Man Machine(人間解体)』のジャケットに用いられた写真のそれ––––とはほど遠く、ラルフは長髪にレザーのライダース、フローリアンは小花柄のシャツというこの時代らしい出で立ちである。この映像では観客も多数映されており(むしろ観客のカットの方が多い)、当時の西ドイツの若者の様子を垣間見ることができるのも興味深いところだ。
ファスビンダー作品の登場人物のようなスーツ
1973年のアルバム『Ralf And Florian』あたりまでは、音楽的にもビジュアル面でも先に述べた傾向を感じさせるクラフトワークだが、明確なコンセプトのもとに制作を進めるようになった『Autobahn』(1974)、『Radio-Activity(放射能)』(1975)の頃になると、ステージ上では『Trans-Europe Express(ヨーロッパ特急)』(1977)のジャケットに見られるようなスーツを着て演奏するようになる。パッドのしっかり入った構築的なショルダーラインのジャケット、裾幅の広いスラックス、ロングポイント・シャツといったそのスタイリングは、さながらニュー・ジャーマン・シネマを代表する映画監督、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーの『あやつり糸の世界』(1973)の登場人物のようであるが、端的にいえば、取り立てて衣裳めいた服装ではなく、その頃の西ドイツの一般的な成人男性のそれ、ということだ。ついでながら、ファスビンダーは『シナのルーレット』(1976)と『ベルリン・アレクサンダー広場』(1980)でクラフトワークの「Radioactivity」を効果的に使っている。
実体のあるものとしての機械、ロボット
1978年のアルバム『The Man Machine(人間解体)』は「人間と機械の融合」といったテーマを掲げた作品。日本盤LPの帯には「機械文明に支配された世界を鋭く描写するクラフトワークのエレクトロニクス・サウンド!」「宇宙時代に向けて、クラフトワークが文明社会への警告を発したスペース・メッセージ!!」とある。しかし、この帯文はやや煽りすぎではなかろうか。そもそも機械と人間ということでいえば、SFの古典でありドイツ表現主義映画の代表作の一つであるフリッツ・ラングの『メトロポリス』(1927)が先行しており、こちらの方が資本家を支える機械を労働者があたかも歯車のようになって動かす、という意味において「機械文明に支配された世界を鋭く描写」しているといえるだろう(ちなみに『The Man Machine』には「Metropolis」という曲が収録されているが、これは映画へのオマージュと考えてよさそうである)。楽曲の歌詞はむしろ淡々としており、警告というよりは、「人間と機械が共存するのが当たり前になった、そんな世界の情景描写」といった趣だ。なお、本作には「マシン」や「ロボット」は出てくるが「コンピューター」という言葉は登場しない。つまり、実体のあるものばかりが取り上げられていて、実際、この頃のライブではメンバーを模したマネキン––––当然ながら同じスタイリングをしている––––を使ったりしているのである。コンピューターについては、1981年のアルバム『Computer World』を待たねばならない。

『人間解体』とロシア・アヴァンギャルド
『The Man Machine(人間解体)』のアートワークは、19世紀の終わりから1930年代に花開いた前衛芸術運動で幾何学性や明確なコンポジションを特徴とするロシア・アヴァンギャルド(ロシア構成主義)を取り入れたものである。フォントやレイアウト、赤、黒、白の3色を基調とした配色など、わかりやすいかたちでロシア・アヴァンギャルドの様式を引用しているわけだが、なにゆえ「人間と機械の融合」とロシア・アヴァンギャルドが結びつくのだろう? そう考えながら『ロシア・アヴァンギャルドと20世紀の美的革命』(ヴィーリ・ミリマノフ著、桑野隆訳、未來社刊)をパラパラとめくっていたら、こうあった。すなわち「全能の科学といったイメージは、ロシア・アヴァンギャルドを直接に鼓舞した要素のひとつである」「ロシアにおける科学信仰は、当時のヨーロッパのどの現象をも凌駕していた」。なるほど、そんなことからあのアートワークになったのかもしれないな、と一人で納得したのだった。
さて、このアルバムジャケットのスタイリングをラフ・シモンズが引用したのはすでに述べたが、ラフ・シモンズはこれ以外にも音楽から想を得たコレクションを発表しており、その意味では何ら特別なことではない。クラフトワークのファッションが一般的に影響力があったわけではなく––––これはアルバム発売当時にも現代にもあてはまる––––、一人のデザイナーがインスピレーション源として光を当てたまでだ。しかし、彼が取り上げることでそれまでクラフトワークを知らなかった、あるいは関心がなかった人々にその存在を知らしめたのは間違いのないところだろう。服を通じて異なる領域の文化への興味を喚起する。そういった文化の橋渡し的な役割がファッションにはあって、そこが面白いのである。

Kraftwerk live | Rockpalast | 1970
https://youtu.be/vNoFHdlMrtI
映画『あやつり糸の世界』予告編
https://www.youtube.com/watch?v=L31wEOxWFn8


