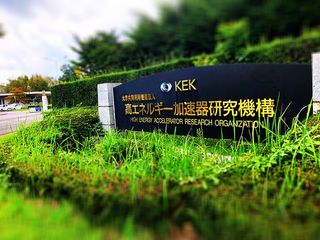朝日新聞の東京本社(写真:西村尚己/アフロ)
朝日新聞の東京本社(写真:西村尚己/アフロ)
「栄枯盛衰は世の習い」という。また「生者必滅」とも言う。
国道16号線沿いで、筆者の住地から50メートルと離れていないところにあるビルの1階を占拠し、四半世紀以上にわたって夜通し煌々と電氣が灯っていた朝日新聞の新聞販売店(ASA)の灯りが令和2年の年明け早々に消えた。
それから数日後、以前と変わらない服装をした一人の青年が屋外で考え込むように坐っていた。
近づいて、「あれ、電氣が消えましたね」と声をかけると、「店長とかが社長と言い合いをしたようです」とのこと。
「押し紙などのことでしょうかね」と聞くともなく一人で言葉を濁すと、「それもあったようです。また齢でしたから」とのことであった。
普段は店頭に自転車やバイクが10台以上並んでいた。そこで「3000部は配布されていたんじゃないですか」と言うと、「いや、もっと。1万部近くあったようです」という。
「そんなに!!」とびっくり仰天した。
そうした矢先の2月24日、自宅の電話が鳴り、女性の声で「朝日新聞の試読をお勧めしています。・・・」という。
無能な経営者?
「朝日新聞の試読」と聞いただけで、同紙の反日的姿勢に嫌悪感を抱いてきた筆者は、反射的に受話器を置いてしまった。
そして、即座に筆者の頭で連想ゲームが始まった。
慰安婦問題で記事取り消しをした以降の朝日新聞の往生際の悪さは月刊誌などで毎号のように書かれており、また部数の激減もしばしば報道されてきた。
そうした経緯から、いつかは朝日新聞も危機に立つかもしれないとは思ってきた。しかし、ASAの閉店と試読の勧誘が重なったことから朝日の現状を知るべく、いくつかの関連資料を探した。