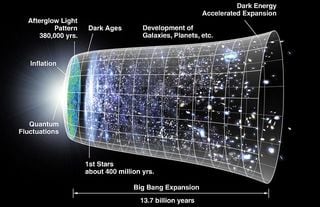(文:鰐部 祥平)
『憎悪の世紀』『マネーの進化史』『文明』などで有名なイギリスの歴史家、ニーアル・ファーガソンの新刊である。もっとも本書は本国イギリスで2003年に出版されていた作品だ。連動して制作されたテレビ・ドキュメンタリー『EMPIRE: How Britain Made the Modern World』ではニーアル・ファーガソン自身が番組の案内役として出演し英語圏各国で多くの視聴者を得た。まさに、ニーアル・ファーガソンの出世作といっていい作品なのである。
そのテーマも壮大で、400年に及んだイギリス帝国の発端から終焉までを政治、軍事、経済、宗教と縦横無尽に駆け巡り論じ、ミクロとマクロの視点を交互にしながら、なぜイギリスが大帝国を築くことができたのか、そして、イギリスが作り上げた帝国は歴史上どんな意義があったのかと、問いかけていく。
イギリス帝国を肯定的に捉えなおす
特に2点目の帝国の意義という問いかけは大変に難しいものであろう。現代社会では、基本的に植民地支配は悪だというコンセンサスが存在する。著者は植民地政策のネガティブな側面も見据えつつ、それでもイギリス帝国を「最初のグローバル帝国」として肯定的に捉えなおし、英語圏の人々に提示して見せたのである。
イギリスの視点で描かれた植民地支配の記述は、非英語圏の読者には反発をおぼえる箇所もあることは確かだ。特にイギリス以外の帝国を人道的に劣った帝国として描いているため、ドイツ、フランスなどはかなり辛辣に描かれているし、日本にいたっては「ボロクソ」という感すらある。訳者の山本文史は、この点を分析しこう説明する。「紳士」「淑女」のイギリス人は、本音をむき出しにすることが少ないのだが、この日本への見方は「イギリス人の本音であろう」とし、「ファーガソンならではの挑発的な書き方」であり、本書の長所でもあり、短所でもあるとしている。