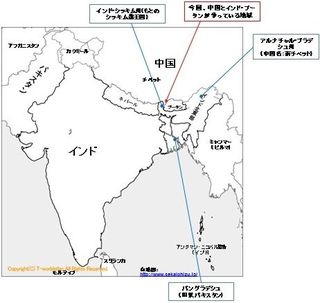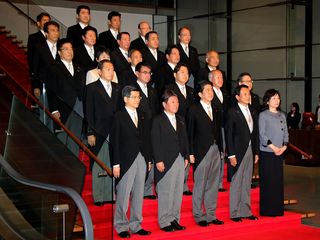オランダの植民地も、フランスの植民地も日本軍が占領して進駐したが、その短い期間中に現地では独立意識が高まった。結果として日本は、東南アジア諸民族の植民地からの独立への道筋をつけたことになる。
オランダは日本軍の撤退後、再び旧植民地に戻ってきて軍事侵攻を行った。だが、最終的にインドネシアは1949年に独立を勝ち取った。フランスの植民地であった仏領インドシナでは、1954年に「インドシナ戦争」が起きる。この戦争でフランスは敗れ、ベトナムから撤退した。
フランス人は、『インドシナ』や『愛人/ラマン』といった映画(いずれも1992年公開)で植民地時代のベトナムをノスタルジーたっぷりに語るが、現在のベトナムにはフランス語の看板など皆無に近い。むしろその後に「ベトナム戦争」を戦った米国のほうが影響力が大きい。ベトナムは実質的に米ドル圏である。
この点は、現在のインドネシアも同様だ。インドネシアでは、意識的に探してみなければ旧宗主国のオランダの痕跡を見つけることはきわめて難しい。
このようにオランダやフランスの態度は、英国と比べると「悪あがき」にさえ映るものがあった。実際には、英国もまた過酷な植民地支配を行っているのだが、「引き際の美学」によってもたらされた違いはきわめて大きい。
大英帝国が残した大きな遺産
現在のインドでは「歴史の見直し」が行われている。端的に表れているのが地名の変更だ。
1995年にはインド西部の大都市「ボンベイ」が「ムンバイ」に改名された。そのほか、東海岸の「マドラス」が「チェンナイ」に、「カルカッタ」が「コルコタ」に改名されている。いずれも大英帝国の「負の遺産」の1つとみなされたためだ。
「歴史の見直し」は、もっぱら「ヒンドゥー・ナショナリズム」がもらしたものだ。このナショナリズムは、1998年に「BJP(インド人民党)」が政権をとる原動力になった。経済の自由化とグローバリゼーションが進展すると、その流れを食いとどめるようにナショナリズムが台頭してくる現象は世界各地で観察される。インドの場合は、多数派のヒンドゥー教徒の覚醒という形で顕在化したのである。
その後、政権交代があったものの、2014年にはナレンドラ・モディ首相率いるBJPが政権復帰して現在に続いている。インドが「世界最大の民主主義国」であるというのは、こういうことだ。同じ新興国であっても、共産党の一党独裁である中国との根本的な違いである。民主主義は英国がインドに残した大きな遺産だった。